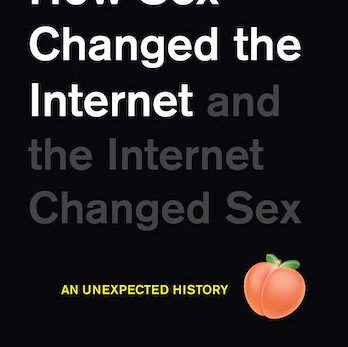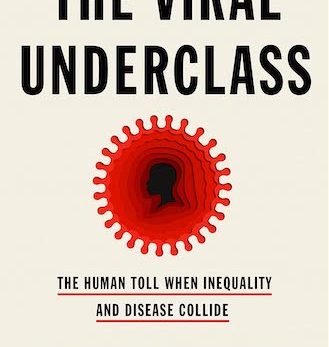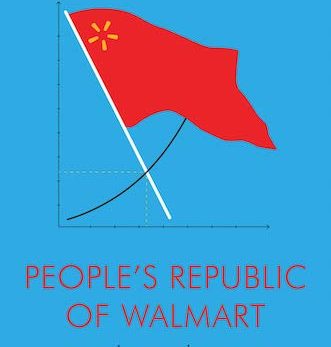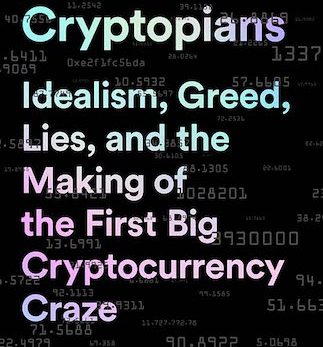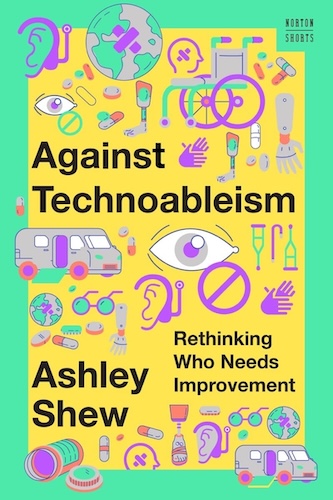
Ashley Shew著「Against Technoableism: Rethinking Who Needs Improvement」
障害を解決されるべき問題と捉えテクノロジーによってその抹消をめざす考えを批判する短めな本。
著者は若手研究者としてこれからという時期に癌の影響で足の切除手術を受け、難聴、クローン病など複数の障害を併発した経験を持つ。わたし自身、障害学や障害者運動の現場には以前から関わってきたのだけれど、著者が詳細に紹介している、手足を切除された人たちが集まるコンファレンスの様子や手足を切断、もしくは生まれつき四肢がない人たちのコミュニティについてはよく知らないので、その点はとても勉強になった。メディアでは義手・義足技術の目まぐるしい発展が華々しく取り上げられ、世間からはおもちゃのロボットのパーツを取り替えるかのように安易に考えられがちだけれど、それは医療の実態とも実際に切断手術を受ける人たちの希望ともかけ離れている。あとScout Bassett著「Lucky Girl: Lessons on Overcoming Odds and Building a Limitless Future」にも書かれていたけど、義手や義足を付けているだけで戦場で負傷した退役軍人だと勘違いして「国のための犠牲」に感謝してくる人がやたら集まってくるらしく、うぜえ。
障害をテクノロジーによって「解決」するという考え方は古い。障害者が生まれてくること自体を出生前診断や強制的断種手術によって予防しようとする直接的な優生思想はやや失速したものの、自閉症などのニューロダイバージェンスを治療したり、テクノロジーを使って障害者を健常者社会に適応させることによってその存在を抹消しようとするソフトな優生思想はいまも社会に根付いている。障害のなかにはそれ自体が苦痛を起こすものもあるが、障害者が経験する困難の多くは社会が健常者に向けて作られているために生み出された社会的障壁であり、障害者を健常者社会に適応させようとするテクノロジーの発展は個々の障害者がより楽に生きるための手段となると同時に、かれらが楽に生きられない本来の原因である健常者社会を温存し強化することにもなる。こうしたテクノロジーの多くは健常者が考える「障害者は何を必要としているか」という思い込みによって設計され、実際にそうしたテクノロジーを使う障害者の声は反映されないため、実際に生み出されるテクノロジーが障害者の期待に反していることも少なくない。たとえば自閉症に対する有効な治療法と称されている応用行動分析(ABA)が同性愛者に対する「転向療法」と類似している点などが分析される。
テクノロジーの発達により障害は次々に「解決」されていくと思いきや、実際には環境破壊や気候変動などの影響により人々の健康な住環境や安全な食は失われ、また長寿化により障害とともに生きる人たちの割合は増えている。COVID-19による長期的な影響もいまのところ研究が進んでいないものの、深刻なものになりそう。障害をテクノロジーによって解決されるべき個々の不幸として扱う考え方は破綻しており、障害者の存在を前提とした社会設計への転換が必要とされている。
最後に出てくる宇宙開発における障害者の役割についての章はおもしろい。宇宙という環境において自力で生活できる人間など存在せず、したがって宇宙に出ればすべての人はテクノロジーによる補助を必要とする障害者であるはずだが、宇宙飛行士に選ばれるのは地球上の軍隊で訓練を受けた屈強な健常者たち。宇宙まで運ぶ重量を減らすことができる小人症の人たちや足で歩かずに動くことに慣れている車椅子使用者たち、トラブルで光が失われても普段と同じように行動できる全盲者など、地上において障害者とされる人たちが宇宙開発プロジェクトに採用されないのはおかしい、という指摘には考えさせられる。実際、NASAでは耳が聞こえない人が乗り物酔いにならないメカニズムを調べて宇宙飛行士の準備に役立てるために難聴者を集めて研究したけれど、難聴者を宇宙飛行士として採用するという考えには至らなかった様子。本書の主題とは少し離れるけれど、障害がどのようにして社会的に構築されるか示す興味深い例だと思った。