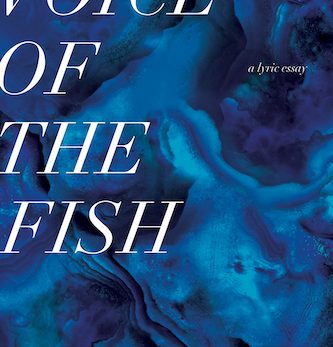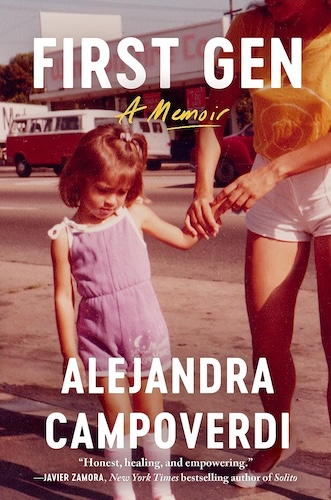
Alejandra Campoverdi著「First Gen: A Memoir」
貧しいメキシコ人移民の女たちの家庭に育ち、家族ではじめてのアメリカ生まれアメリカ育ち、はじめての大学卒業、はじめての大学院進学を経て2009年のオバマ政権の誕生とともにホワイトハウスのスタッフにもなった著者が、「はじめての、唯一の」例外として成功することの難しさと孤独について振り返る本。
著者はメキシコ出身の祖母や母、叔母らに囲まれてロサンゼルスで育つ。彼女たちが付き合った男たちは無責任で、自分の子どもやその母らを捨ててまた別のところで別の女性と子どもを作り、育児費その他の支払いはしない。著者自身も子どものころ実の父親と会ったことは数回しかなく、会っても彼女になんの関心も向けないばかりか、「育児費を払うよう請求するのを母親にやめさせろ」と言ってくる始末。大人たちが必死に働いても高等教育を受けていない移民女性である彼女たちが働ける職は限られ、生活は苦しい。
著者はそういうなか、一時は力強く生きるメキシコ系ストリートギャングに憧れてリーダーの男と付き合ったりメンバーになろうとするなど、世間が彼女のような背景を持つ人に抱くステレオタイプ通りの人生を歩みそうになったが、家族の愛情を受け努力を続け、南カリフォルニア大学に進学する。大学では周囲に大学卒業者が普通にいるほかの学生たちならみんな当たり前に知っているキャンパスライフの常識を知らずに戸惑ったりからかわれたりしながら、勉強とアルバイトに励んで家族で初の大学卒業者となる。
ある出会いを経てビジネススクールへの進学を考えるも、大学院進学のために必要な数学は彼女が高校で習っていた(大学では高校の単位が認定してもらえたので履修しなくてよかった)数学とはまったく別物。同じ数学でもこんなにレベルが違うのかとショックを受けながらも猛勉強するなか、ハーヴァード大学のケネディスクール(公共政策大学院)に興味を抱き、入学を認められる。自分がハーヴァードに入学できるなんて、ついに自分は認められた、と思ったものの、普通に豊富な海外旅行の経験があり国際関係に詳しいほかの学生たちとの違いに再び愕然。自分と同じような「はじめての、唯一の」背景を持つ学生たちにも出会えたものの、今度はかれらとの競争にさらされる。
彼女がケネディスクールに在籍したのは2007年から2008年。その時期、民主党のバラック・オバマ上院議員がまさしく「はじめての、唯一の」黒人大統領となるべく大統領選挙に立候補しており、著者はかれが語る理想に魅了され卒業後に選挙スタッフとなることを希望する。しかし当時、オバマ陣営のもとにはほかにも多数の理想主義的かつ有能な若者が押しかけていて、オファーされたのは無償のボランティアのポジション。その秋からは当初の予定どおり奨学金を得てビジネススクールに進学することを決めていた著者は、多額の学生ローンを抱えながらシカゴに移動、生活費をクレジットカードでまかないながらオバマ当選のために力を尽くす。秋になりビジネススクールがはじまると、一時は選挙運動から離脱するも、いまはビジネススクールにいる時ではないと考えて退学、選挙運動に戻る。この時彼女は、学生ローンを返すあても仕事を見つけるあてもなく、あと数ヶ月で終わる選挙のために全てをなげうったことになるが、彼女と働いていた多くの同僚たちは親に生活費を頼っているなど資産のある家庭の人たちが多かった。
そしてオバマは当選。大統領就任式の直前になって著者はホワイトハウスから仕事のオファーを受ける。しかし著者が仕事をはじめてすぐ、彼女の過去がメディアで騒がれる。彼女は学生時代、できるだけ効率のいいアルバイトを探した結果モデルとして一時期活動していて、そのなかである男性誌で下着のようなコスチュームを着た撮影をしていた。新政権が一番嫌うのはこういうゴシップで余計な騒ぎに巻き込まれることで、彼女はクビを覚悟するも女性である直属の上司が彼女を擁護してくれ、なんとか辞職を逃れるが、それでも彼女はその後も写真について同僚に噂話をされ、能力ではなくセックスアピールで仕事を得たと陰口を叩かれる。のちに彼女が下院議員に立候補した(20人の候補が出馬する乱戦で、落選した)際にもこの話題が蒸し返されるだけでなく、政治資金を集めるかわりにホテルに泊まれと言ってくる「支援者」がいたり。これに対して著者がコスモポリタン誌に寄稿した政治におけるミソジニーについての記事は注目を集めた。
これだけ見ると不利な背景に生まれた著者が困難を押しのけて成功した話のようだけれども、切ないのはその困難そのものではなく、成功した結果として彼女が自分を支えてくれた家族に対して抱く罪悪感と孤立感。家族は大学に行くところまでは応援してくれたけれど、大学院に行くと言い出したところ大反対。そんなのは無駄だ、そんなことよりすぐに仕事して家族を助けてくれ、というのは自分たちの娘が大学院に進学することなど考えたこともない家族の当たり前の感情だった。彼女はたしかに成功を収め、自分自身が家賃や食費を払えなくなる不安からは自由になり、病気になったらすぐに専門医に診てもらえる立場になったけれども、かといって親戚全員を貧困から救えるほど稼いでいるわけではないし、かれらだってそんなことは望んでいない。家族や親戚が抱える一つ一つの問題についてであれば経済的に支援することはできるけれども、その全てを解決するには到底足りないため、どれを支援してどれを拒むのか悩む。どうして自分だけが、という思いとともに、レストランで食事をしたり海外旅行をするなど贅沢をするたびに、このお金があれば家族や親戚がどれだけ救われるだろうか、という問いに苛まれる。
著者をふくめ「はじめての、唯一の」例外的な成功例として称賛されている人たち、あるいはそうした立場を目指す人たちが直面する構造的な困難と、成功の結果として生まれる新たな孤独について正面から取り上げ、同じ境遇に置かれた人たちに共感を伝える自叙伝。とても大事な内容が詰まっている。