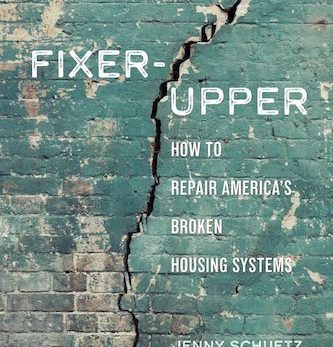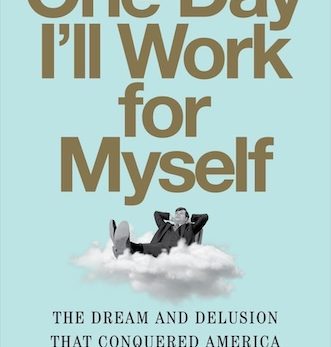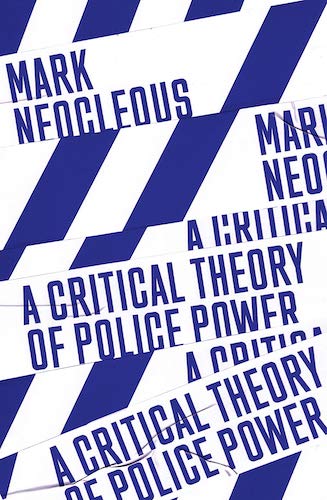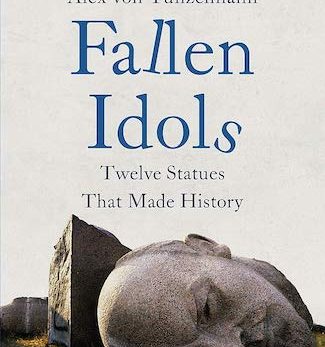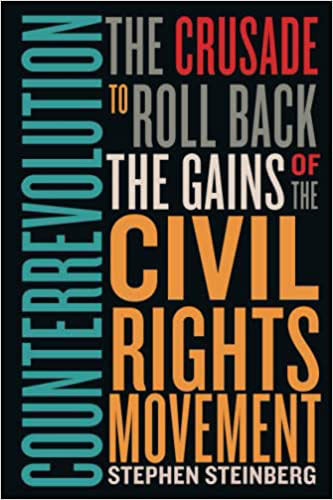
Stephen Steinberg著「Counterrevolution: The Crusade to Roll Back the Gains of the Civil Rights Movement」
公民権法や投票権法が成立して黒人の権利が確立された1960年代以降、アファーマティブアクションへの攻撃や投票妨害などにより一度は達成された権利が後退している状況を、黒人解放の革命に対する反革命と規定し、保守派だけでなく白人リベラルもがそれに加担してきたことを糾弾する本。著者はこれを、20世紀前半に活躍した黒人運動家・社会学者W.E.B. Du Boisが歴史的名著「Black Reconstruction in America」(1935)で分析した、逃亡奴隷やその他の黒人たちが南北戦争に参戦することで勝ち取ったリコンストラクションがその後12年で巻き返された第一の「黒人解放革命と反革命」になぞらえ、黒人の権利獲得に対する第二の反革命として論じる。
公民権運動に対するバックラッシュについて論じるうえで政治や社会のさまざまな部分に注目することができるけれど、(おそらく)ユダヤ系(だと明記されてはいないけど内容と名前から推測される)の社会学者として社会学とユダヤ系インテリの責任を強く指摘している。W.E.B.Du Boisの当時からずっと、かれをはじめとした黒人社会学者や一部の白人社会学者をのぞくと、社会学では黒人の経験については人種差別ではなく「人種関係」という枠組みで議論されており、黒人たちが置かれていた不利な状況は差別や隔離政策ではなく黒人たちの側に問題があるとされていた。それを公民権運動がピークを過ぎたあとに政策の場に持ち込んだのが、ニクソン政権で労働次官を努めていた社会学者(のちに上院議員)のダニエル・パトリック・モイニハンが書いたいわゆる「モイニハン・レポート」だった。
またアファーマティブアクションについて、先日立教大学アメリカ研究所が開催した公開シンポジウム「『アジアン・ヘイト』とはなにか——『いま』の依拠する歴史と構造」で南川文里氏がエリート大学においてアファーマティブアクションによってアジア系アメリカ人が不自然に合格率を下げられている、という訴えについて取り上げていたが、この議論はアジア系アメリカ人の存在感が高まったことによって起きたものではなく、人口の3%に過ぎないユダヤ系アメリカ人がエリート大学に多すぎるという反ユダヤ的な攻撃や、ユダヤ人がニューヨークなど一部の地域に集まって住んでいることを念頭に「地域ごとにクォータを設けるべきだ」などという議論(白人キリスト教徒救済のためのアファーマティブアクション)が以前からあったところに、アファーマティブアクションによって黒人のための枠が設けられると損をするのはユダヤ系だというかたちで、黒人とユダヤ人のあいだを分断しようとする動きもあった。(著者はこの分断について、それに乗ってアファーマティブアクションを攻撃したユダヤ系インテリたちを厳しく批判している。)
この本ではほかにも、ユダヤ系やアジア系の「モデルマイノリティ」的な成功神話や「貧困の文化」論、カラーブラインド論など、人種差別の被害者たちを犠牲者非難したり、黒人の自由と権利を保証するための取り組みを否定するための論理を社会学が提供し続けていることを指摘。その一方で、2020年にミネアポリス市警によるジョージ・フロイド氏の殺害をきっかけに起きたブラック・ライヴス・マター運動の盛り上がりについて著者は、第三の革命とまではさすがに呼べないとしても、反差別運動や社会学の一部でしか知られていなかった「制度的レイシズム」という言葉と概念を一般に広めたという点で評価している。レイシズムと反レイシズムが同じ軸の上で押し合っているのではなく、それぞれが論理としても運動としても別個に発展を続けている、というイブラム・ケンディの議論を引いて、BLM運動が全国で広く支持された一方、各州で参政権の行使を妨害する法律が作られ、トランプ支持者らが連邦議事堂を武力占拠する事態を経た現在も、革命と反革命が同時進行する最中にあると説明する。