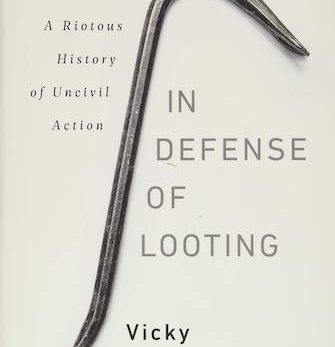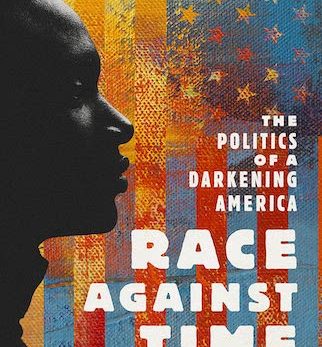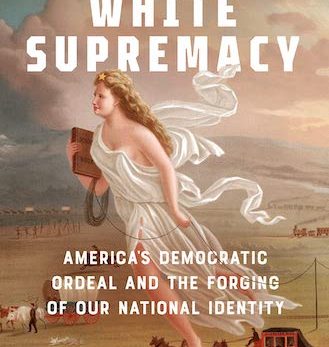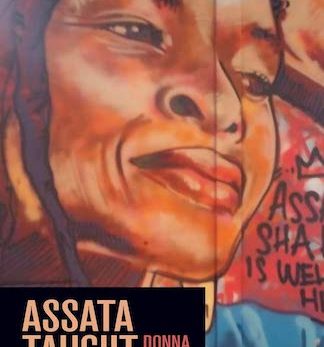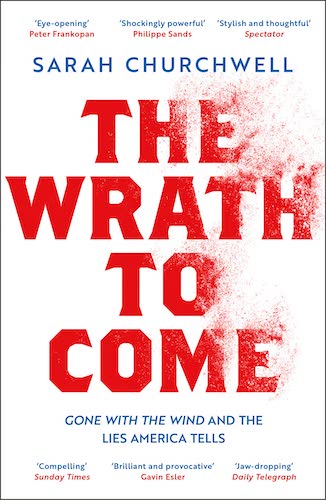
Sarah Churchwell著「The Wrath to Come: Gone with the Wind and the Lies America Tells」
20世紀アメリカを代表する長編小説『風と共に去りぬ』が書かれた時代とその背景とともに、この小説に代表される南部白人たちの「失われた大義」(ロスト・コーズ)と被害者意識、そしてそれらを支える奴隷制度とリコンストラクションについての歴史的な嘘を、連邦議事堂に米国史上初めて南軍旗をたなびかせた2021年1月のクーデター未遂とトランプが扇動した「大きな嘘」に繋げて論じる本。『風と共に去りぬ』に描かれているような、奴隷制を美化し、南北戦争後にKKKなど白人至上主義者たちが起こした黒人に対するリンチや虐殺を「白人女性を守るため、不正な投票をさせないため」と正当化した「失われた大義」の論理は過去の歴史の話ではなく、メキシコ系移民をレイピストだと排除したり黒人が多い都市部での投票に不正があったとして暴力的な政府転覆を扇動したトランプやかれを支持する白人たちの論理と直接繋がっていることをこれでもかと暴く。
『風と共に去りぬ』の舞台はジョージア州アトランタ。主人公スカーレット・オハラが生涯愛した農園タラ・プランテーションは南北戦争の結果として北軍の占領によって荒廃し、財産を失ったスカーレットは苦しみながら北軍と黒人解放奴隷に対する被害者意識を抱えたまま事業に恋にと波乱の人生を歩む。アトランタには南軍の将軍たちを称えるために作られた世界最大の壁画が山壁に描かれたストーンマウンテンがあり、第二・第三波のKKKが発足した聖地であるとともに、キング牧師がかつて率いた教会がある街でもある。キング牧師は有名な「わたしには夢がある」のスピーチで「ストーンマウンテンから自由の鐘を打ち鳴らせ」と叫んだ。また2020年にはアトランタからの支持によりバイデン元副大統領がジョージア州を取り大統領に当選したほか、キング牧師の教会の現役牧師であるワーノック議員ら二人の民主党候補が上院の議席を獲得した。ジョージア州、そしてアトランタがアメリカの歴史において白人至上主義とそれに対抗する運動の両面で果たした役割は大きい。
『風と共に去りぬ』が現代のトランプに思想的に繋がっていることは、トランプ自身も示唆している。2020年に韓国映画『パラサイト 半地下の家族』がアカデミー賞を受賞した際、トランプは自身の集会で「ただでさえ貿易で韓国とは問題を抱えているのに」と文句を言ったうえで、「『風と共に去りぬ』みたいな映画はどうした?」と問いかけ、支持者たちから大きな拍手を浴びた。一見排外的な愛国主義を披露しているようなこの発言は、しかし『風と共に去りぬ』がアメリカ合衆国に対して謀反を起こした南軍を美化し、アメリカ合衆国の軍隊である北軍を腐敗した占領者として非難する内容の作品であることを考えればわかるように、愛国主義的な発言「ですらない」。南北戦争に敗北した南部の白人たちがそれでも自らの大義を主張したように、アメリカの憲法的秩序を踏みにじり暴力によって国民の選択を否定しようとしたトランプやその支持者たちが、自分たちの嘘に国を巻き込もうとしている。
南部白人の「失われた大義」が南部だけにとどまらず一世紀ほどのあいだ学問的な正統性を得て北部にも広まったのは、『風と共に去りぬ』の小説や映画のせいではない。それは南北戦争後、奴隷制の廃止だけで満足してしまった北部の白人たちが、黒人たちの権利を保証するよりも南北の和解を優先し、そのために南部の嘘に同調してしまったからだ。トランプ政権時代のさまざまな人権侵害やホワイトハウスによる違法行為、選挙結果の否定や連邦議事堂占拠に繋がる一連のクーデター未遂を「終わったこと」だとして「未来指向」で責任追及はやめようと共和党主流派政治家たちが言うなか、とても考えさせられる本。