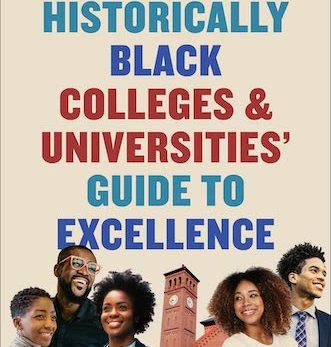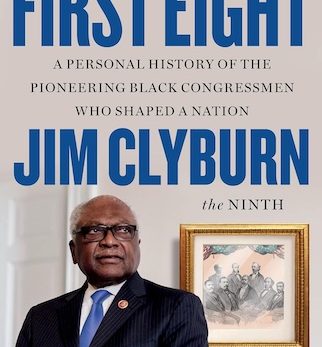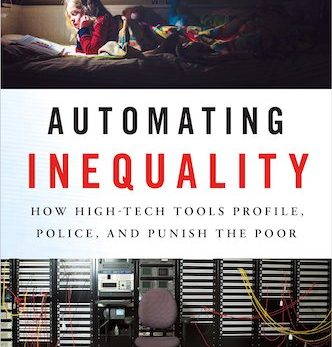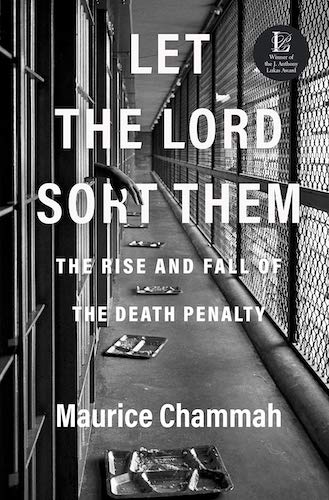
Maurice Chammah著「Let the Lord Sort Them: The Rise and Fall of the Death Penalty」
1972年に最高裁がFurman v. Georgia判決で全国の死刑制度を停止してから現在までのアメリカにおける死刑制度についての議論、裁判、メディアの扱いなどを論じた本。タイトルに「Rise and Fall」とあるけど、1972年に停止された死刑制度がその後社会や司法の保守化の流れにのって復活・拡大を遂げ、ところが90年代末からDNA検査によって死刑判決を受けた人たちの無実が次々に証明されたり、警察や検察の不正が明らかになるなどした結果、死刑廃止とまではいかなくともより慎重に、かつ重大事件のみに限って運用するべきだという世論が高まるまでをカバーしている。
もともとFurman判決で死刑が停止されたのは、死刑の適用に一貫した基準がなく、人種や偶発的な状況によって被告間の扱いが大きく異ることが違憲であるとされたため。だから一貫した基準を決めて人種や主観的な判断が介在しないようにすれば良いはずだといくつかの州でそうした新法が作られたけれど、基準が一貫していても刑事司法のさまざまな段階で人種的偏見は排除できないし、情状酌量の余地が狭められてさらに不公平感は高まった。これは死刑制度だけでなく刑事司法制度においてよくある問題で、差別や主観的な判断を取り除こうとして個別の判断を禁止し機械的な判断を導入したところ、融通の効かない厳しすぎる制度になる一方、差別や偏見はその機械的な判断に盛り込まれてしまっている、というのはよくある話。
死刑廃止とまでいかなくとも、より慎重に、そしてより例外的なケースだけに適用するべきだ、という考えが広がっている、というのは、つい最近まで死刑はできるだけ多いほうがいいと言っていた大統領がいて、それに同調してそうな最高裁判事が3人も増えたいま、あまり実感しないけど、そういえばそうだった、90年代のクリントン時代の、民主党と共和党が競って「より犯罪者を厳しく裁け」と言っていた時代からはかなり変化している気がする。まあそのせいで、当時そうした風潮をリードしていたヒラリー・クリントンやバイデンが時代遅れになって叩かれたわけだし。
最高裁にしても、オバマ政権の末期には中道リベラルのブライヤー判事が死刑制度に批判的になり、より保守的なケネディ判事もそちらに動きはじめていたところに保守派のスカリア判事が亡くなったので、共和党が妨害せずにガーランド判事の任命を認めていれば、その時点で死刑制度が大きく制限されていた可能性が高かったらしい。まあマコネルとトランプのせいでそれはなくなり、しばらくのあいだ死刑制度は安泰だろうけど、世間の風潮としてはそこまで現状の死刑制度に対する批判が広まっていたというのは、90年代と比べたら確かだと思い出した。