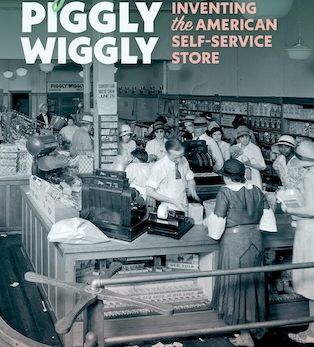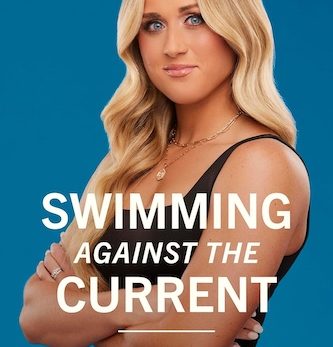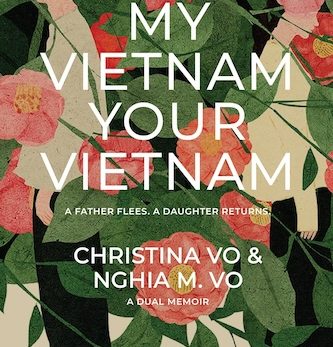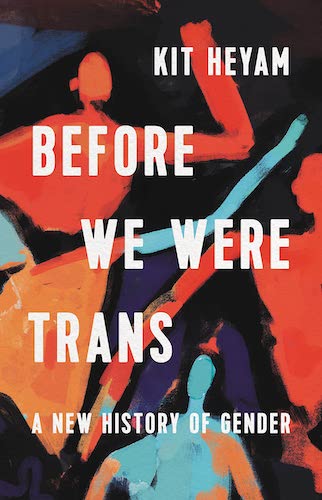
Kit Heyam著「Before We Were Trans: A New History of Gender」
イギリスのノンバイナリー・トランスを自認する歴史家が描き出す、新しいトランスジェンダーの世界史の本。トランスの歴史を記そうという試みはこれまでにもあったけれど、トランスジェンダーというカテゴリや性自認という概念が歴史的・文化的に現代欧米型社会に特有のものであり過去や他の文化圏には適用できないという問題や、資料として残されている情報の多くが医療記録や裁判文書によるものであり当事者自身の思いや考えがそのまま反映されているとは考えにくいことなど、さまざまな困難が存在する。
そういうなか本書は逆に、ジェンダーはバイナリーであり生まれつきであり固定的である、という近代欧米的なジェンダーの決まりに収まりきらない事例を日本を含むアジアやアフリカ、ヨーロッパ、アメリカなどから広く収集し、著者を含む現代のトランスやノンバイナリーの人たちが自らのコミュニティに繋がる歴史としてそれらを受け入れる、という新たな「トランスの歴史」の捉え方を提案する。
これは、現代のアイデンティティコミュニティが歴史的人物を「取り戻す(reclaim)」動き、たとえば誰々はトランスジェンダーだったとかレズビアンだったというように過去の人物を現代のカテゴリに当てはめて自分たちの先駆者として扱うものとは異なる。現代のカテゴリを過去の人に当てはめることは適切ではないし、「取り戻す」という表現自体が過去の人物に対する排他的な所有権の主張として機能してしまい、結果として誰々はトランス男性だ、いやブッチレズビアンだ、あるいは別の誰々はゲイだ、いやバイセクシュアルだ、というような取り合いに発展してしまう。
こうした対立は、このところ著者の住む英国で増えている反トランス派活動家たちによって広められている、レズビアンや女性の性役割を好まない女性が「お前はトランス男性かノンバイナリーだ」と社会的に決めつけられて不本意な形で医療的なトランジションに追い込まれている、という認識と、女性が女性として自由に生きるためにはトランスやノンバイナリーの承認が否定されなければならない、という政治的な動きにも関わっている。しかし著者の考えでは、ある過去の人物が「トランスの歴史」に繋がることは、その人物はたとえばトランス男性であり女性やレズビアンではない、ということには必ずしもならないし、同じ人物が「女性の歴史」や「レズビアンの歴史」に繋がることもありえる。
現代の反トランス派の政治運動においては、トランスの存在は医療の発達と個人主義の「行き過ぎ」によってごく最近になって生まれたもので、それまでは歴史的に一貫してジェンダー(あるいはセックス――この区別自体も20世紀以降の新しいものだけれど)はバイナリーで生まれつきで固定的であるのが当たり前だった、と前提されることが多い。しかし本書が(そして過去の多くの類書が)多数の事例を挙げながら指摘するとおり、こうした前提こそが近代西欧的なジェンダー解釈の特徴だ。「トランスの歴史」を現代の定義でいうところのトランス(性役割や性的指向から区別された、性自認の問題)に留めず、「バイナリーで生まれつきで固定的とされる近代西欧的なジェンダー制度の外側の歴史」と規定することは、はるかに豊かな歴史的伝統をもってヘイトに対抗することを可能にする。ただしその際、非西欧的な事例を植民地主義的に簒奪する危険、そして文化的文脈や宗教的な意味から切り離された「ジェンダー」視点からのみそれらを認識する危険には気をつけなければならない。
トランスの歴史について書かれた本は、最初に挙げたような理由や、最後に挙げた植民地主義的な問題によって「なんだかなー」と感じるものが多いのだけれど、この本はわりとすっきりと読めた。ただ最初のほうで「黒人フェミニストたちは、わたしたちのジェンダーの経験や理解が人種と切り離せないことを長年強調してきた」と書いている部分で、黒人フェミニストの例としてキンバリー・クレンショー、オードリ・ロード、ベル・フックスらと並べてわたしの名前が挙げられていて、こんなすごい人たちに並んで名前を入れてもらってこんな光栄なことはないと思う一方、わたし黒人じゃないんですけど…という。わたし、明らかに日本人名だし、まさか黒人と間違えたわけじゃないと思うけど、なんか全体の信頼性に関わるので第2版が出るなら直してほしい。本自体はオススメなんだけど、さすがに恥ずかしいので。