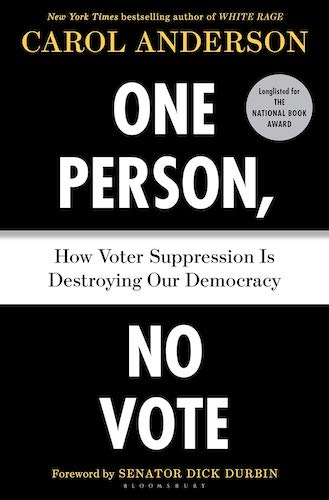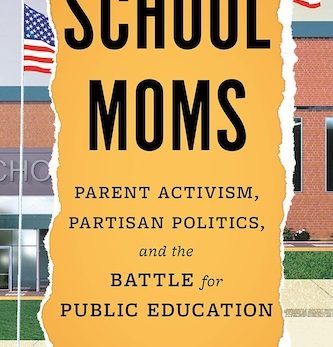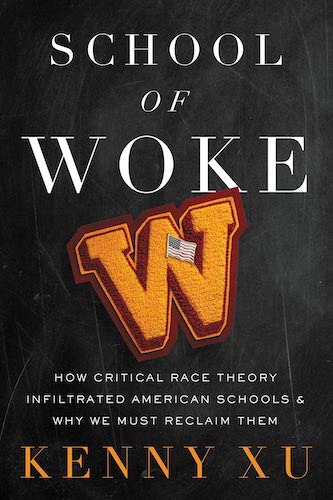
Kenny Xu著「School of Woke: How Critical Race Theory Infiltrated American Schools and Why We Must Reclaim Them」
今年六月に人種を大学入学審査の要因に含めるアファーマティヴ・アクションを禁止する最高裁判決が出た裁判(Students for Fair Admission v. Harvard)にも原告側(アファーマティブアクション禁止論側)で関わった中国系アメリカ人の保守活動家が、教育における批判的人種理論(CRT)を批判する本。
前著「An Inconvenient Minority: The Harvard Admissions Case and the Attack on Asian American Excellence」は黒人やラティーノを優遇するアファーマティヴ・アクションによって努力して成功を勝ち取ろうとしているアジア系アメリカ人が差別されている、という主張が中心にあり、人種問題に関する認識の浅さや飛躍した論理は見られたものの、アジア系アメリカ人の生徒や親の気持ちを代弁しているところはあり、アファーマティヴ・アクションの是非について一応きちんと議論していた。しかし本書では、前著では何度かしか使われていなかった(そしてそれに違和感を感じた)「ウォーク」や「批判的人種理論」という右派や白人至上主義者が多用する犬笛的なキーワードを連発し、教育において人種差別の問題を扱う人たちにはこういう隠れた動機がある、という陰謀論が全般に渡って展開されており、ほとんどまともな議論となっていない。
著者によると、批判的人種理論の裏には子どもに対する支配を親から奪い国家のものにしようとする共産主義的・全体主義的な目的があり、なんでも人種差別のせいにすることによって教育の失敗の責任から逃れようとする教師や学校当局と、人種差別を無くすための教師や子どもに対するさまざまなプログラムや書籍などを提供することで教育予算を私物化しようとする「人種差別産業」があるという。またクィア理論は批判的人種理論の一部であり、子どもたちのジェンダーやセクシュアリティを尊重するという名目のもとに親に内緒で相談させ、親から子どもたちを引き離す目的がある。民主党やリベラルが子どもたちを親から奪い公有化しようとしている証拠として挙げるのは、アフリカの諺とされる言葉「子どもは村中みんなで育てるもの」タイトルとしたヒラリー・クリントンの著書「It Takes a Village」(邦訳「村中みんなで」)で、著者はこれを「悪魔的な」言葉だと批判する。
もちろん現実に一部には人種差別に取り組むプログラムを行っている教師や外部の団体が何か問題を起こしたケースや、教育に関わる人たちが個人的に繋がっている外部のプログラムを優遇したケース、人種差別について授業で取り上げた結果子どもがショックを受けたがフォローされなかったケースなど、問題が起きないわけではないのだけれど、それらの事例を全体主義的な目的や教育予算の私物化のために意図的に起こされたものだという著者の主張には根拠がない。問題を起こす教師は人種差別に取り組むプログラムでなくてもいくらでもいるし、校舎の建設や学校の備品購入、あるいは差別と関係ないプログラムのための外部業者の選定などにおいても同じように腐敗は起きている。校内で起きている問題や外部業者との契約の透明化などは行われるべきだが、それが批判的人種理論(と著者が呼ぶもの)と特に関係するとは考えにくい。
人種差別についての取り組みが子どもたちの間に対立を生み出し傷つけている、という主張についても、人種差別について取り組まないことだって対立を深刻化させ子どもたちを傷つけることもあるのだから、議論するなら「どのようにやるべきか、ショックを減らすためにどうするか、ただ人種差別について取り上げるだけでなく生徒をどのようにフォローすべきか」という方向に議論すればよいのだが、著者は特に問題が起きたケースを挙げて、それがどれだけ一般的な事例なのか論証もせず、全面的に禁止すべきだと主張する。反差別の文脈で、多数派だけれど少数派に対する差別に反対する人をよく「アライ(味方)」と呼ぶが、著者はその言葉を根拠に「味方がいるなら敵がいるということだ、CRTは子どもたちを人種によって分断して敵味方を生み出している」と言う。
単純な事実の間違いも多い。2012年にコンビニに買い物に行った黒人のトレイヴォン・マーティン少年を追い回し射殺した自称自警団団員ジョージ・ジマーマンのことを警察官だと書いたり、オードリ・ロードの名言を誤用したり、オバマ政権で教育長官となったアーン・ダンカンは教師や学校区に結果責任を求める教育改革論者で教員組合からめっちゃ嫌われてたのにCRTを押し付けただけの人にしてしまっていたり、あとブッシュ43rd政権の「No Child Left Behind」政策がオバマ時代に置き換えられたのは、民主党だけでなく共和党も共通テストを使って学校教育の質をチェックする仕組みの問題点に気づいたからだし。
さらに、人種差別を疑われるのを恐れて学校は黒人生徒の問題行動を処罰できなくなり、その結果問題行動は増加した、という主張の論拠が、「黒人生徒の問題行動の処罰が増えた」というデータだったりするのは、なに言ってんだとしか。「人種差別産業」に教育予算が流れるようになったことで優秀な黒人やその他のマイノリティが医師や弁護士など伝統的なエリート職を目指さずに「人種差別産業」を通して教育予算を食い物にする方向に動機づけられてしまった、と言うのだけど、事実とてもそうなっているようには思えないし、著者がその例として挙げるのがハーヴァード法学校を好成績で卒業したにも関わらずシカゴの黒人地域でコミュニティ・オーガナイザーとして働くことを選んだバラック・オバマ。いやコミュニティ・オーガナイザーは教育予算と関係ないし、かれはシカゴ大学で教鞭を取りながら政治家に転身し大統領になるというエリート街道を走りきったんだけど、この人知らないの?
本書に妥当な内容が皆無かというとそうではなく、たとえば女子や人種的マイノリティの生徒が学びやすいようにアプローチを変えた数学教育のプログラムや、英語を第二言語とする子どもに対する二か国語教育について、本書が指摘するとおり、良かれと思ってあるプログラムを実施してみた結果さらに数学や英語の習得が遅れてしまったというケースはある。しかしそれらは教育学や教育の現場において日々どうすればより優れた教育を行えるのか議論されているなかでの試行錯誤であり、決して著者が言うように「人種やジェンダーを通して子どもたちを対立させ、また親の支配から引き離して、食い物にしようとして行っている」わけではない。前著でも白人至上主義や陰謀論に片足踏み込んでいたような印象を受けていたが、本書は全力で両足揃えて大ジャンプしてしまっており、タイトルがタイトルだしおそらくわたしの意見とは相容れないだろうと予想しつつそれでも何か得るものがあるのではないかと思ってたけど、心底がっかりした。