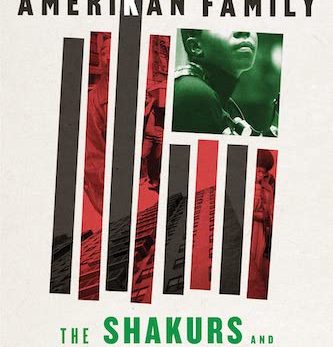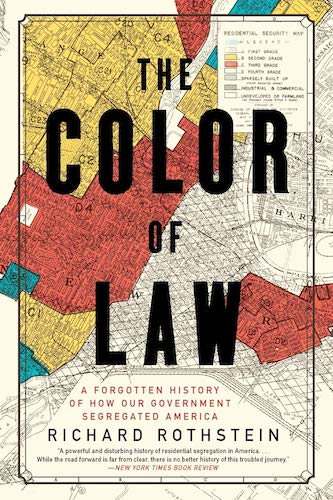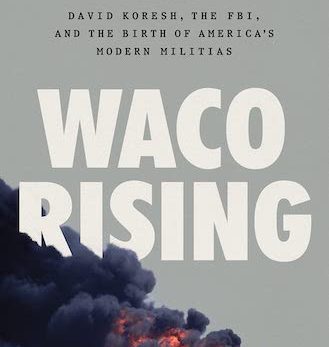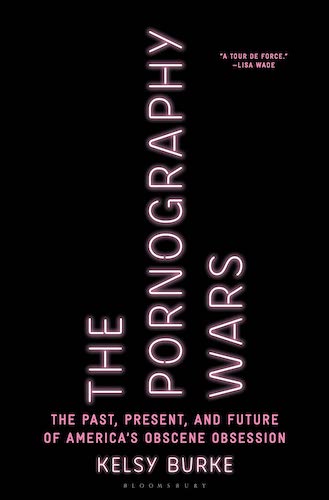
Kelsy Burke著「The Pornography Wars: The Past, Present, and Future of America’s Obscene Obsession」
アメリカにおけるポルノグラフィをめぐる議論の歴史と現代についての本。
タイトルで「ポルノグラフィ戦争」と煽り、ポルノ賛成派と反対派という構図でそれぞれの主張を分析しながら、「実際には対立しているばかりじゃなくて双方が同意している部分もあるよ」とまとめてみせるあたり、マッチポンプ臭い。いやいや、そもそも賛成派vs反対派の戦争という構図に落とし込んだのあなたでしょ?お互い必ずしも相容れない宿敵ではないという例示として、裁判でも争ったラリー・フリント(『ハスラー』誌で有名なポルノ業界のボス)とジェリー・ファルウェル(反ポルノ・反同性愛などの立場に立つ宗教右派の代表格)が仲良くなってハグしたとかいう逸話を入れられても、女性のセクシュアリティを支配しようとする二人の男がつるんでいるようにしか見えないわけですけど。
まあ面白い部分もあって、たとえばよくラディカルフェミニストと宗教右派がそれぞれ異なる理由から「反ポルノ」の立場で一致して協力した、という話がよく言われていて、それが現代の反性労働や反トランスジェンダーの動きと比較されることもよくあるんだけど、実際のところラディカルフェミニストと宗教右派はほとんど共闘してないよ、という指摘。共闘した例として有名なのは、インディアナポリス市の保守系の市議がラディカルフェミニストで法学者のキャサリン・マッキノンにポルノ規制の条例案(ポルノ製作者に対して被害を受けた人が民事裁判に訴えられるようにする案)を書いてもらったという例だけれど、逆に言うとその程度しか例がなくて、たとえば反ポルノのイベントを共催したり共同声明を出したりということはなかった。反性労働や反トランスジェンダーの活動で保守と共闘している現代のフェミニストたち(全部ではないけど)は、昔の反ポルノ運動の再来ではなく、それよりさらに劣化している。
また、Heather Berg著「Porn Work: Sex, Labor, and Late Capitalism」でも詳しく書かれていたけれど、ビデオや雑誌からインターネットのポルノサイトを経て、俗に「チューブサイト」と呼ばれるポルノ動画アップロードサイトに人気が集まり、さらに一社がその大部分を独占するという現状がポルノ市場やポルノ労働のあり方に与えた多大な影響が指摘されている。本来なら健全な市場や労働者の権利を守るはずの政府が「性的人身取引撲滅」を口実として誰の利益にもならない介入を続けるあまり、状況を悪化させ続けている。
悪い本ではない、というか変にポルノ擁護やポルノ批判の立場に寄っておらず、フェミニズム内の論争だけでなくより広い議論を紹介しているという意味で、あまりポルノ論争について知らない人にとってはいい本じゃないかと思う。わたし的には、「ポルノに対する立場がどうであれ、みんなセクシュアリティは大切なものだと思っている」とか当たり前のように言われてしまうと、いやそうとは限らね―だろって思ってしまうわけだけど。