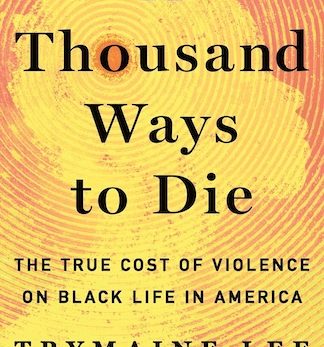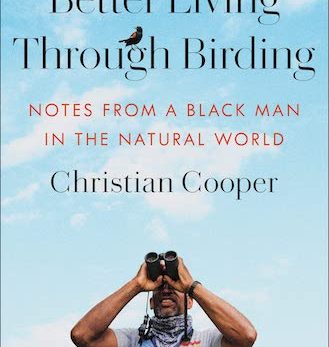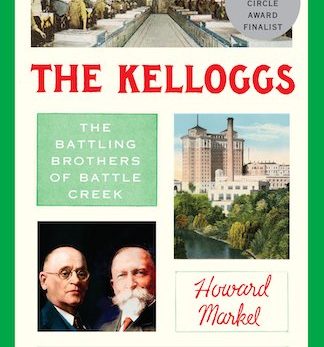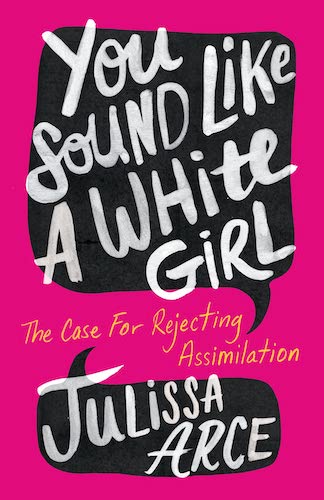
Julissa Arce著「You Sound Like a White Girl: The Case for Rejecting Assimilation」
子どものころメキシコ人両親に連れられて観光ビザで入国した米国で育てられ、有名大学を卒業したあとウォールストリートで就職し結婚を通して永住権を取得した著者が、それまでの人生で追求してきた「アメリカ=白人社会への同化」の欺瞞に気づき、移民の文化的同化を強要しながらもどこまでいっても白人と対等には扱おうとしない主流社会に厳しい批判を向ける本。タイトルはかつて英語の発音にメキシコ人っぽい訛りがなく「白人の女の子みたいに聞こえる」と言われたことを褒め言葉と受け止め、誇りにすら思っていた過去の自分を告白するもの。
自分たちの子どもに最大限の機会を与えようとアメリカに移住する一家と、かれらの期待を背負って「自由と平等」というアメリカの建て前を信じてそれを追求し、外野から「移民はこうあるべき」と称賛される程度には成功しながらも、そうした生き方は自分の一部を否定して自分をコミュニティから切り離すだけでなく、自分を成功例として称えることが自分が属するコミュニティの他の人たちを押さえつける駒にされてしまっていることに気づき、そうしたアメリカの建て前を拒絶する、という構図は、トリニダード出身の黒人移民女性が書いたTiffanie Drayton著「Black American Refugee」とも共通。トリニダードとメキシコのそれぞれのアメリカ帝国主義との異なる関係やメキシコ人と黒人の違いはあるけれど、どちらのストーリーもとてもよくわかる。
主流(白人)社会への同化は多くの移民にとって個人としてのステータスを向上させる手段としてある程度有効で、だからこそ魅力ではあるのだけれど、本当に成功して受け入れられるのはごく一部の例外だけだし、その人たちもほんの少しのことですぐにそのステータスを失ってしまう。これは集団としても同じで、アメリカ史において多くのマイノリティは「自分たちは黒人とは違う」ということに縋り、少しでも頂点に居座る白人たちに近づこうとしてきたけれども、それは黒人に対して差別的であると同時に、結局白人を頂点にしたピラミッドを強化することになってしまう。たとえば自分たち〜人移民はこんなに社会に貢献している、こんなに真面目に勉強したり働いている、という移民擁護論は、「移民は社会に寄生している、真面目に働かず福祉や犯罪で生活している」というレイシストたちの攻撃への反論としては必要かもしれないけれど、それは移民を人間としてではなく道具として扱うことにもなり、またアメリカ社会における黒人への偏見を前提として「われわれ〜人移民は黒人とは違い白人と同じ価値観や習慣を持っている」というアピールにもなりかねない。
この本では歴史に埋もれたメキシコ系アメリカ人やメキシコ系移民たちによる白人至上主義への抵抗の歴史についても紹介されており、一番印象的なのは1968年にテキサス州クリスタルシティでメキシコ系の高校生たちが起こした運動。クリスタルシティの住民の85%がメキシコ系だったのだけれど、市や教育委員会の指導層はほぼ全員白人。当時女子高校生の憧れのポジションとされていたチアリーダーのチームではメキシコ系の生徒は一人しかチアリーダーになれない決まりがあり、ほかにもさまざまな制約をつけて対抗戦などで学校を代表するチアリーダーは白人がつとめるような仕組みになっていた。どうしてもチアリーダーになりたかったメキシコ系の生徒・ダイアナさんをほかの生徒たちが支持し、授業ボイコットなどの運動を続けた結果、学校側は人種割り当てはやめないものの、白人とメキシコ系のチアリーダーを同数にすると決定。ところが白人生徒の親たちが「学校の恥になる」と抵抗し、それを受けて地域の教育長が学校の決定を撤回させると、それに対してさらなる抵抗運動が起こり、人種割り当ての廃止だけでなく、バイリンガル教育、メキシコ系アメリカ人に関する授業、カフェテリアでメキシコ料理の提供をはじめる、など多数の要求が実現した。この勢いはさらに街を巻き込み、2年後には教育委員会や市議会にも多数のメキシコ系アメリカ人が進出した。わたしはこのすごい歴史をはじめて知ったのだけれど、それだけでもこの本を読む価値があったと思う。(でもこれだけじゃないのでみなさんも全体を読んでください。)