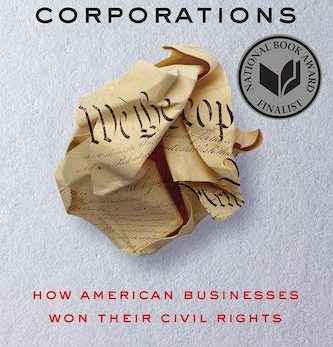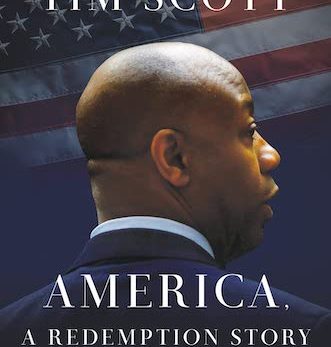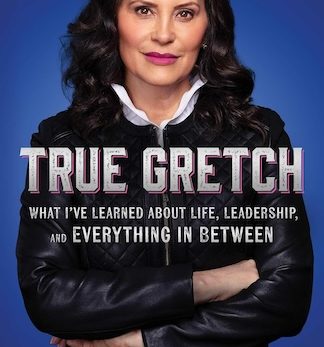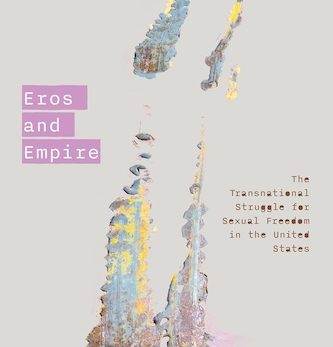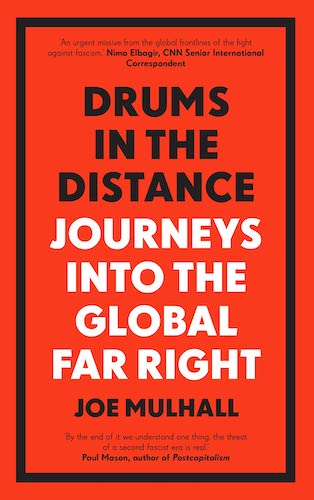
Joe Mulhall著「Drums in the Distance: Journeys into the Global Far Right」
国際的なファシズムや極右運動に対抗するためのイギリスの団体HOPE not hateに所属する著者の本。欧米だけでなくインドや(コロナ禍のせいで著者自身は渡航できなかったけど)ブラジルなど各地で極右団体に潜入したり極右集会に参加して情報収集しそれらを暴露することで極右運動に打撃を与える活動について書かれている。以前読んだ「Culture Warlords」を書いたTalia Lavinも白人至上主義団体に潜入しているけど、この本の著者はアメリカの武装した極右団体による「国境警備」活動に参加するなど、おかしている危険がさらに大きい。著者が白人男性で組織的バックアップを受けているからこそできたこと。デモなどで右派や警察と衝突しているアンティファ(も場合によっては必要なんだけど)とは違い、組織だって戦略的に動いている活動ってすごいと思った。
この本では、欧米の極右運動についての記述ではそれらがどのように国際的に繋がり連動しているのか、反社会的な極右運動と主流社会に浸透しつつある極右政党・政治家の関係はどうなのかなど、興味深い内容が書かれているいっぽう、ISIS(イスラム国)の活動の影響を取材するために著者がイラクに渡った部分や、インドやブラジルの極右政権についての記述は、すでに他のジャーナリストによって報じられている以上の内容はなかった。著者が所属している団体では世界中の極右政治運動や過激主義をその対象としているのだけれど、欧米以外の国では著者ら白人活動家が潜入することは難しく、同じ欧米人ジャーナリスト以上の情報収集能力はないはず。イギリスや欧米に拠点を置く反ファシズム・反極右運動の団体が欧米以外の人権活動家や抵抗運動をどうやって支援していくか、というのは大きな課題だと思うのだけれど、著者にはそういう観点はなさそうだった。
著者のイスラム系過激主義に対する批判や、どうしてそうした批判を極右に独占させてはならないのかという議論は一部同意できるし、理解するのだけれど、欧米の極右や白人至上主義について扱うなかでは「それは唯一の原因ではないし言い訳にしてはならない」と言いつつもシリア難民危機によるヨーロッパ社会の混乱やアメリカ中西部の構造的失業などの問題を指摘しているのに、イスラム過激主義がどうして広まったのか、一部で支持を受けているのかについては同じような分析がない。イスラム過激主義を白人至上主義と同列に並べるどころか、白人至上主義のほうにだけそれが発生した原因も考えるべきだという共感的な態度を示しているように見える。インドやブラジルで極右政権が支持を集めた原因の分析も、トランプやオルバーン(ハンガリー首相)が選挙で選ばれた原因の分析に比べて少ない。白人男性だからこそできることと、白人男性だからこそ見えなくなっていることの両方が浮き彫りになった本だった。