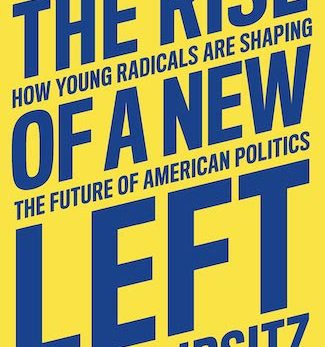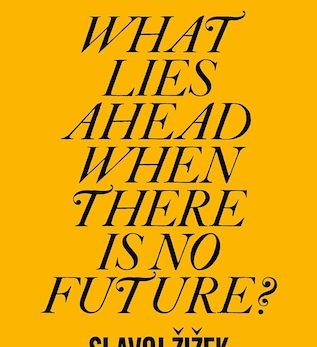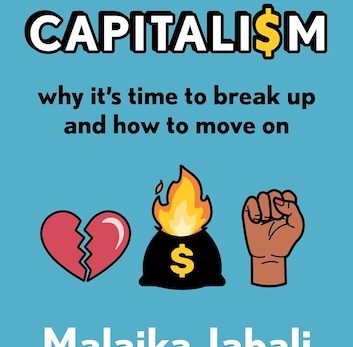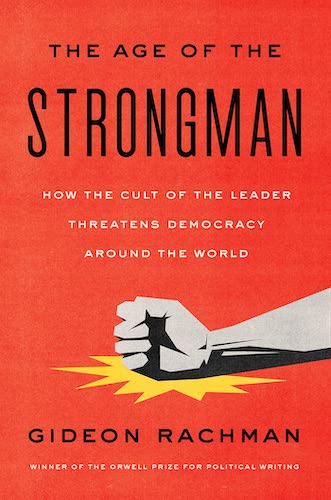
Gideon Rachman著「The Age of The Strongman: How the Cult of the Leader Threatens Democracy around the World」
21世紀になって世界で増えつつある強権的な政治リーダーについての本。取り上げられているのはそれぞれが強権的リーダーとしてトップに上り詰めた時期順にプーチン、エルドアン、習、モディ、オルバン、ヤロスワフ・カチンスキ、ボリス・ジョンソン、トランプ、ドゥテルテ、ムハンマド・ビン・サルマーン、ネタニヤフ、ボルソナロ、アンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール、アビィ・アハメド。それぞれの国は民主制だったり一党独裁制だったりその中間だったりするのだけれど、欧米リベラリズムとグローバリズムに反対して国内のマイノリティを迫害し、法廷やメディアなどを弾圧し指導者に対する個人崇拝を進めている、という共通項で結びつけている。この中でジョンソンだけは強権的な傾向がある割に思想や決断力に欠けていてここに含めていいものか異論もある、と著者が認めているのは、ジョンソンの評判にとって良いことなのかどうなのか。より古典的な独裁者、たとえば金正恩などは省かれている。
これらの強権的リーダーの少なくない人物が、はじめは民主的な改革派として欧米エスタブリッシュメントに歓迎されてきたという指摘はおもしろい。有能なテクノクラートとしてエリツィンが残した混乱をおさめてくれると期待されたプーチンはじめ、トルコを近代化させると期待されたエルドアン、腐敗撲滅の取り組みが評価された習近平など、次第に政敵の収監・追放や暗殺、マイノリティ迫害や他国への軍事関与、憲法改正による権力の終身保持などをとおして強権的な傾向を強めていく。これらの指導者たちが司法やメディアの力を奪って権力の座にしがみつく様子を見るにつけ、アメリカで起きたトランプによるクーデター未遂は本当に危なかったんだなあと思うと同時に、(政府でなく)政治制度の安定性というのは民主制の存続のために本当に重要だなと改めて思う。
多くの強権的リーダーが敵として名指しするジョージ・ソロスについての章もおもしろい。ハンガリーのユダヤ人家庭に生まれ幼少期にナチスの占領とソ連の侵攻を経験し、学生時代にはカール・ポパーの「開かれた社会」の影響を受けたソロスは、アメリカのウォール街で世界有数の投機家として成功したあと、「開かれた社会」を意味するオープンソサエティ財団を設立して東欧の民主化運動をはじめ世界各地で自由と民主主義を広げるための運動を支援した。当初はアメリカの保守派にもそうした活動は評価されていたけれど、21世紀に入るとロシアのプーチンをはじめ強権的リーダーたちによって世界支配を目論む陰謀の中心人物と名指しされ、欧米の保守系(や、時に左派系)メディアにも激しく叩かれる。ソロスに対する攻撃は多くの場合より古典的な反ユダヤ主義的陰謀論の焼き直しなのだけれど、イスラエルのネタニヤフはオルバンなどそれらを宣伝する強権的政治家とむしろ協力的。それは「イスラエルはユダヤ人のもの、ハンガリーはハンガリー人のもの」という形でかれらがお互いの排外主義を尊重しあっているから。トランプが国内向けには中国を非難しつつも習近平個人に対しては(プーチンやボルソナロや金正恩に対してと同じように)褒めちぎりウイグル人に対する弾圧を容認した背景にも、強権的リーダー同士のリスペクトがある。
最終章ではトランプが違法に権力の座に居座ろうとして失敗したことを受けて強権的リーダーシップの今後が論じられている。バイデン大統領は民主的価値観を掲げプーチンや習との対決姿勢を強めているけれども、そのためにアジアではモディやドゥテルテ、ウクライナ戦争ではオルバンやポーランドの「法と正義」党政権との協力をしており、自国に都合のいい国の強権政治には甘いというアメリカの伝統的なダブルスタンダードを露呈している。著者は第二次世界大戦後の20世紀の歴史を「冷戦体制のもと西側が社会民主主義的な改革を進めた30年」「エネルギー危機をきっかけにサッチャー・レーガンなど保守的指導者がネオリベラリズムを進めた30年」と区分しており、プーチン以降の世界をそれに続く「強権的リーダーの時代」と規定している。この時代がどれだけ続くかは分からないけれども、強権政治は強権的であるゆえに権力者が間違った政策を取った際にそれを止める勢力が生まれず、結果として問題が取り返しのつかないほど悪化してしまうこと(これらの国家のコロナ対策の失敗はその一例)、またそうなった場合に市民の支持を維持するために敵を作り出すことで内戦や戦争を起こすこと、そしてどんな強権的なリーダーもいずれば衰えていくことなど、長期的には決して安定した体制とは言えない。とりあえず2024年にアメリカで変なことが起きることだけは勘弁してほしいとつくづく思う。