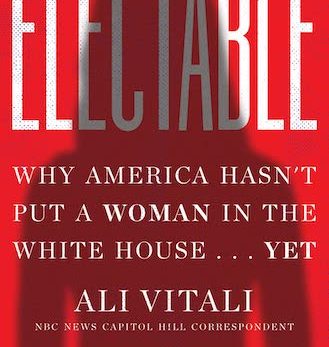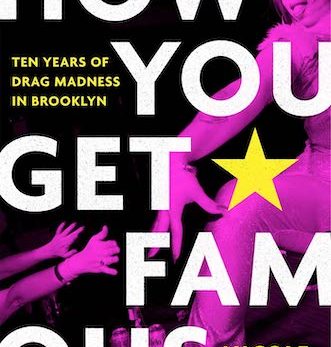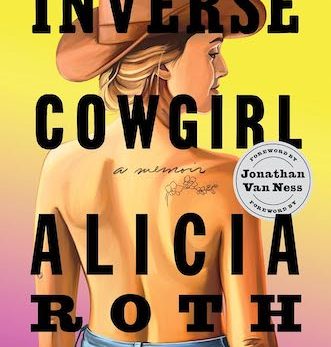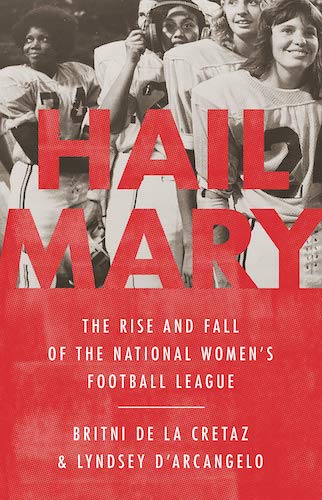
Britni de la Cretaz & Lyndsey D’Arcangelo著「Hail Mary: The Rise and Fall of the National Women’s Football League」
1974年から1988年まで存在した全米女子(アメリカン)フットボールリーグ(NWFL)の忘れ去られた歴史を掘り起こす本。女性がフットボール競技に参加した記録はフットボールと同じくらい古くからあるけど、大学スポーツやプロスポーツとして大人気を博し巨額のお金が動いている男子フットボールと違い、女子フットボールはほとんど注目を集めて来なかった。たまに女子フットボールチームが結成されても、一度きりのお祭り的なイベントだったり、手を抜いた男子と対戦させるなどコミカルな見世物として企画されたり、下着や肌を露出させたコスチュームで競技するようなものだったりと、真剣なスポーツとして扱われてはこなかった。ドールズとかペティコーツといったチーム名もそうだし、チームを宣伝する広告に実際の選手ではなくユニフォームを着た美人モデルが採用されたりもした。そういうなか、女性選手をギミックとして扱って手早く金儲けする手段としか思っていなかったプロモータの意図を超えて、真剣にフットボールをやりたい女性たちが集まり、一時的とはいえ各地に広まったのがNWFLだった。
本書に登場する女性たちは、子どものころ兄弟や近所の男友達とともにフットボールで遊んでいたけれど年齢が上がると女性が競技できるチームがなくフットボールから離れてしまった人や、ソフトボールやサッカーなどより女性の競技環境が整っているスポーツに参加していたけれどフットボールチームの結成を聞いて参加した人など。学生から主婦やさまざまな職種の女性たちで、一部の街ではレズビアンバーでフットボールチーム結成について知ってトライアウトに参加した人も多かった。NWFLの記録はスコアや勝敗など基本的な情報すら報道されていないことが多く、全体でチームがどれだけあったのかすら分からないのだけれど(チームの結成とリーグへの参加が発表されたあと潰れた例が結構ある)、著者は古いメディアの記事を調べるだけでなく、かつて選手だった女性たちを探して取材したり、彼女たちが自宅の倉庫に保存していた資料を見せてもらったりしている。
NWFLに参加した女性たちは、人種や性的指向はさまざまだったが、ほとんどは労働者階級の人たちだった。女子フットボールは当時のメディアによって、その頃活発になっていた女性解放運動の象徴として描かれるとともに、その「行き過ぎ」の例として嘲笑されたが、実際のところ選手のあいだでは白人エリート階層が目立つ女性解放運動やフェミニズムに対する関心は低かった。また、チームのなかでは人種や性的指向をめぐる対立はそれほどなかった、と彼女たちは言うけれども、現在まで続いている元チームメイトの仲良しグループは見事に人種と性的指向で分かれているというのがリアル。
リーグの運営ははじめから一貫して厳しく、一度も利益をあげることがないまま崩壊していった。そもそもの投資規模が小さく、道具は高校チームの使い古し、遠距離の遠征試合の予定は交通費が出ないと中止され、労災保険料の支払いをなくすためにプロ契約だったはずがセミプロにされたりもした(怪我しても自己責任!)。しかし結成当初何年ものあいだ利益が出ないのは、男子のプロスポーツとして成功しているフットボール・バスケットボール・野球などの歴史でも同じで、リーグを新設するならそれだけの資金を準備するべきだった。なぜなら女子フットボールを競技として広めるにはそれなりに年月がかかって当たり前だし、地元チームに安定的にファンが付くにはさらに年月がかかる。女子フットボールという話題性でヒットさせて儲ける、という短期的展望しかないプロモータにはそのような準備などなく、話題性が霞んだらすぐにほかの事業に移っていった。
「これが最後の試合」という予告もなく、突然リーグの解散が発表され選手たちはチームメイトとお別れする機会もないままNWFLが崩壊して30年以上。そのあいだに女子フットボールのリーグはいくつも結成されたけれども、今に至るまで商業的にプロスポーツとして成立している例は一つもない。女子の団体プロスポーツとしてそこそこ成功しているのは、メーガン・ラピノーのようなスーパースターが生まれ人気を博する女子サッカーのNWSLと、男子プロバスケリーグNBAの全面支援を受けた女子バスケWNBAくらいだ。また、フットボールという競技自体、繰り返し頭をぶつけ合うことによって起きる慢性外傷性脳症(CTE)が注目され、「見世物のために若い黒人男性が脳を壊される」競技だと批判されている。女性がフットボールを競技することによるCTEやその他の身体的ダメージについては男性のそれに比べてもさらに分かっておらず、ともすれば「女性を守るため」という口実で女子フットボールに対するバッシングが起きかねない。女性の健康を守るための研究や必要ならルール改正などは進めるべきだが、かつて「女性が走ると子宮が壊れる」という理由で女性のスポーツ参加が否定されたことを繰り返してはいけない。
わたし個人的には、クィアである(らしい)著者二人が愛をもって描写しているフットボール選手になったブッチレズビアンたちの話が、むかしレズビアンバーに連れて行ってくれたブッチたちのことを思い出して、なんだかうれしかった。わたしの知っている人にフットボールをやっていた人は(わたしの知る限り)いなかったけど、昔の(主に白人労働者階級)レズビアンコミュニティはバーのほかにはソフトボールを通して集まっていたところがあって試合を見に行ったことがあったので、ああ、あの人ならフットボールをやる機会があったらやってたかもなあ、と思い出した。