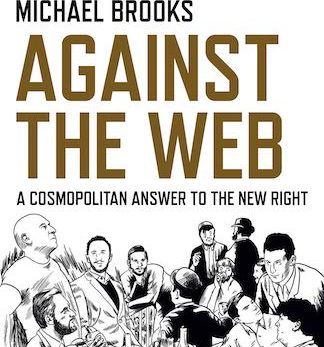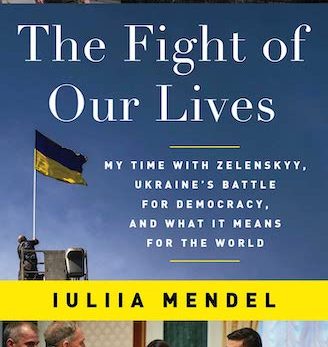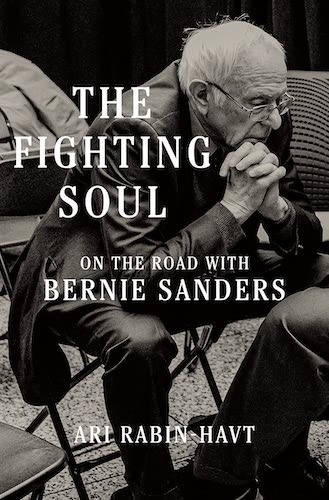
Ari Rabin-Havt著「The Fighting Soul: On the Road with Bernie Sanders」
バーニー・サンダースの2020年の大統領選挙で陣営の副参謀を務めた著者がバーニーと過ごした2年間を振り返る本。いやもう、80歳近いのに大統領選挙の最中に自宅の雨漏りを直そうと椅子を積み上げて屋根の上に上がろうとして聞かなかったり、1954年にロサンゼルスに本拠地移転したブルックリン・ドジャーズ(サンダースはブルックリン出身)の帽子を着用してロサンゼルス・ドジャーズのキャンプを見学して球団からロサンゼルスの帽子を渡されても受け取らなかったり、コンサルタントの言うことは聞かないし政治的に不人気な主張をメディアで堂々と言うし(受刑中の囚人も投票権があるべきだ、フィデル・カストロは良いこともした、など)、側近からも「どうしてうちのボスはこんなに部下泣かせなんだろう」と言われつつ、「でもそんなバーニーだから力になりたい」と思われているサンダースが最強すぎてヤバい。
活動家として公民権運動に参加した1960年代からバーリントン市長になった1980年代、そして連邦議員となった1990年代以降と、こんなに変わらない政治家も珍しいし、いっぽう、大統領になったわけでも党指名を受けたわけでもないのにこんなに二大政党の1つの方向性に影響を与えた政治家もまた珍しい。ふつう、これだけ両党の主流から離れた主張を続けていると議会のなかで孤立していそうなものだけれど、実際はそうでもないらしい。かれくらい主張がはっきりしていてしかも一貫していると、対極的な主張の政治家からもリスペクトされるんだなあというのは、わたしがワシントン州議会で議員たちと話をしてきた経験からも納得できる。このオーセンティシティは魅力的。
2020年の民主党予備選では、進歩派のサンダースやウォレンに対し、中道派のバイデン、ハリス、ブーティジェッジ、ブルームバーグ、クローブシャー、その他という二つのレーンでそれぞれ支持者を奪い合っている、という形で報道されてきたけれど、サンダース陣営が一貫して警戒していたのはバイデンだった。それは元副大統領で知名度があるというような理由ではなく、出身階級文化的に「ビール派かワイン派か」と分けた場合に同じ「ビール派」としてサンダースと最も競合するのがバイデンだったから。予備選挙の最初の3州、アイオワ、ニューハンプシャー、ネヴァダでサンダースは勝利し15の州・地域で同時に予備選挙が行われるスーパーチューズデーでは大票田のカリフォルニアを狙い撃ちし有利に立つ、という予定だったのが、その直前に中道派の候補たちが次々に脱落しバイデン支持を表明したことで、決着がついてしまった。このままだとサンダースが民主党指名を取ってしまう、その場合トランプが再選されてしまう、という民主党主流派の懸念がいかに大きかったかわかる。2016年の共和党予備選挙では有力候補がゴタゴタ小競り合いを続けているうちにイロモノ扱いされていたトランプが党指名を取ってしまったことを教訓にしたのかも。
本書によると、バイデンがサンダースを労働長官に指名する、という計画は本当にあったらしい。サンダースは労働長官になったら労働者の側に立った大改革を進めるつもりで準備をしていたけれど、ジョージア州上院議員選挙の決選投票で民主党が2議席独占したことで計画が崩れる。せっかく民主党が上院を支配できることになったのに、サンダースが上院を離れたら共和党に奪い返されてしまうので、議員を続けざるをえなかった。民主党が上院を取ってサンダース自身も上院予算委員長になったのは良かったけど、かれが労働長官になるのも見てみたかった。