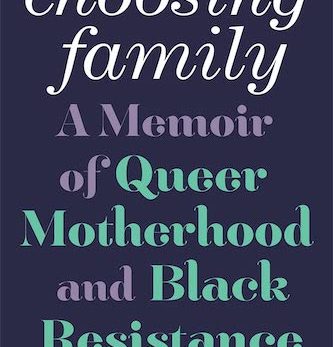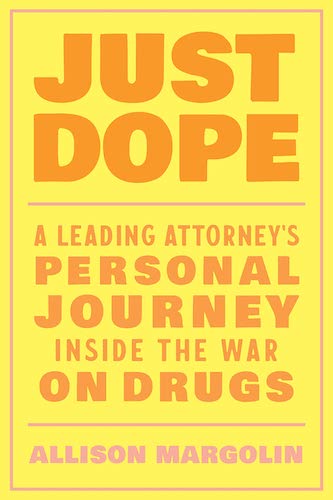
Allison Margolin著「Just Dope: A Leading Attorney’s Personal Journey Inside the War on Drugs」
かつてティモシー・リアリーを弁護した著名な弁護士で大麻合法化活動家の父親を持ち、自身も大麻使用者や合法化された大麻ビジネスの弁護を専門とする弁護士が、自ら見てきた「麻薬との戦争」の影響を語る本。
大麻合法化運動についてはそれほど知らないのだけれど、彼女の父親は運動内ではかなりの大物だったらしく、偉大な親を持った子どもの苦悩的な個人史的な話と、彼女が弁護士として経験した話の2つが文中で混ざり合っている。父親との関係においては、ハードドラッグに手を出したせいで大麻合法化を主張するもののハードドラッグには厳しい父親に見下された経験や、インドを長期間旅行したこともあるヒッピーであり物欲を否定しながらビバリーヒルズの豪邸に住み高級車を乗り回す父親に感じた不審感などが書かれてたりで、まあなんてゆーか、彼女の気持ちはわかるんだけど、恵まれた環境で育った人のお話ですねとしか。
弁護士として経験した内容では、麻薬使用者や大麻ビジネス関係者の弁護をするなか見聞きした、おかしな法律によって生活を脅かされる人たちの話はそこそこおもしろい。また、彼女は子どもが欲しくなり精子目当てで(相手もそうだと了承したうえで)セックスした男性との関係がこじれて親権をめぐる争いになったのだけれど、そのなかで彼女や彼女のパートナーに対して「妊娠中に麻薬を使っていた」「パートナーが麻薬を密造している」といった言いがかりをかけられていて、自分は弁護士であり知識もリソースもあったので不当な言いがかりに対抗することができたが、もし自分が貧しい非白人の女性だったら「麻薬との戦争」の犠牲になっていただろう、という話も。
本書で一番おもしろいなと思ったのは、大麻所持で逮捕されていた人たちの弁護で活躍していた彼女が、カリフォルニア州内での大麻合法化が実現したときの気付き。それまで彼女はつねづね大麻合法化を主張してきたのだけれど、いざ実際に合法化が実現すると、彼女の仕事が激減。政府による「麻薬との戦争」と戦っていたはずなのに、親のお金で通った大学やロースクールの費用を含め、自分の生活基盤のすべてが実際には「麻薬との戦争」に寄生したものであったと気付かされた。いや気づくの遅くね?と思うけど、大麻は合法化されたあとも複雑な規制が続いているので、それ以降も大麻ビジネスの弁護で著者はちゃんと食べていけてる様子。
「麻薬との戦争」が黒人やラティーノなどマイノリティに大きな被害をもたらしていることや、麻薬規制の歴史が人種差別や反移民主義と結びついていること、パーデュー・ファーマやインシスなどオピオイド鎮痛剤を売っている製薬会社が競争相手となる大麻の合法化に反対していることなど、政治的な背景についての話もあるけれど、扱いは軽め。本書の一番のポイントは、中心人物の娘の視点からみた大麻合法化運動の内幕(前から言ってるけど性暴力とかに甘くてかかわり合いになりたくない)。