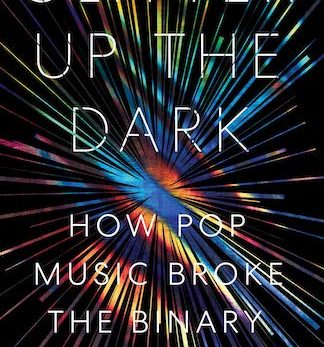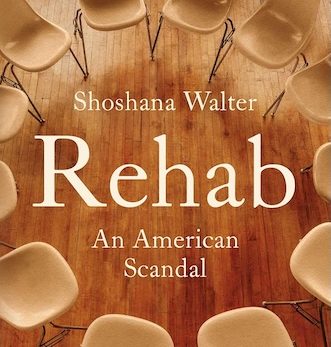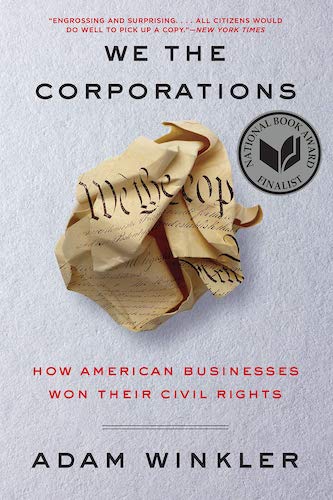
Adam Winkler著「We the Corporations: How American Businesses Won Their Civil Rights」
アメリカのビジネスがどのようにして法人としての「人権」を勝ち取ったか、という刺激的なタイトルの本。2010年のCitizens United裁判で最高裁は、過去の判例を撤回し、憲法に保障された「言論の自由」には企業などの法人が政治や選挙に関わる言論行為に資金を出すことを規制されない権利が含まれる、という判決を下した。この判決はリベラルだけでなく一部のポピュリスト保守からも「企業は人間ではない、人権は人間のものだ」と反発を呼んだ。また続いて2014年にはHobby Lobby裁判において、企業オーナーの信仰の自由を理由として、健康保険制度から避妊具など信仰に反する項目を除外する権利が最高裁に認められた。この件も、オーナー個人には信仰の自由があるが企業は個人ではないので信仰の自由を認めるべきではないという批判が起きた。これらの判決は個別に見ると過去の判例を大きく変更する内容であり、「人権は生身の人間だけに認められる」とする憲法改正案が提案されるほど反発を浴びたが、この本は、これらの動きは19世紀から続く「憲法の人権保護条項を企業に適用させようとする請求」の延長線上にある、とする。
アメリカ史において、マイノリティの権利が裁判によって認められた例には、たとえば人種隔離政策を違憲とした1954年のBrown判決や、同性婚の禁止を違憲とした2015年のObergefell判決などが知られるが、それらはマイノリティの権利を求める社会運動がある程度広がったことを背景に生まれた判決。そもそも資金や支援者の不足などからマイノリティが裁判に訴えること自体が難しいし、社会運動が浸透するまえに裁判を起こしても却下されるだけ。それに対し企業は政府による規制に対抗するために、豊富な資金を投入し多くの裁判を起こすことができるので、たとえば奴隷解放ののちに制定された「法の下の平等」を定めた憲法修正14条を根拠とした裁判は、黒人による公民権運動が広がった20世紀中盤までのあいだ、ほとんどが企業による訴え(自社が政府の規制を受けているのに、他の企業や他の産業にかからないのは不当だ、という内容)だった。
著者によると法人の「人権」をめぐる最高裁の議論において2つの論理が拮抗していて、ひとつは法人をその株主や経営者とは別個の個としての権利主体であるとするもので、もうひとつは法人が持つ権利はそのオーナーの個人の権利を代表しているとするもの。Citizens UnitedやHobby Lobby判決のあと、「法人は人間ではない、人権は人間だけにある」という批判が多く聞かれたけれど、実は最高裁判決は法人の個としての権利を認めたのではなく、法人に代表されるオーナー個人の権利を認めた内容だった。だからこそHobby Lobby判決ではオーナー個人の信仰の自由が認められたわけであって、人間ではない企業に信仰は持ち得ない。公民権運動の時代に州政府によって黒人人権団体が潰されそうになったときも、人権団体(は団体なので人種はなく、当然人種差別の対象として保護されない)ではなくその団体が代表する黒人たちの権利が侵害されたから裁判所が介入できた。
つまりCitizens United判決を批判する人はよく、「法人に人権を認めるな」と言っているけど、実際には法人を権利主体として認め、オーナー個人の権利を代表させないほうが、そしてそのうえで憲法修正によって法人の権利をある程度制限したほうが、法人を権利主体として認めない(オーナーの権利を代表させる)より良いのかもしれない。
企業が人権を守るための憲法の条項を利用して、憲法に一切書かれていない「法人の権利」を推進してきた歴史は、最近読んだ「Presumed Guilty」に描かれた歴史とパラレルだし、消費者活動家として一斉を風靡したラルフ・ネイダーが裁判闘争を通して実現した「消費者の権利」が企業の「人権」推進に利用されていくパターンも同じく最近読んだ「Public Citizens」に書かれていたものと通じ合っていた。