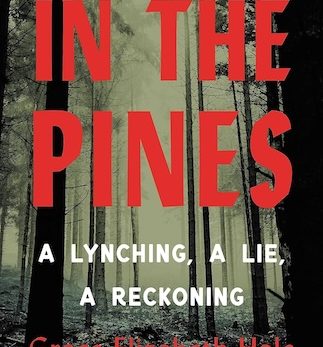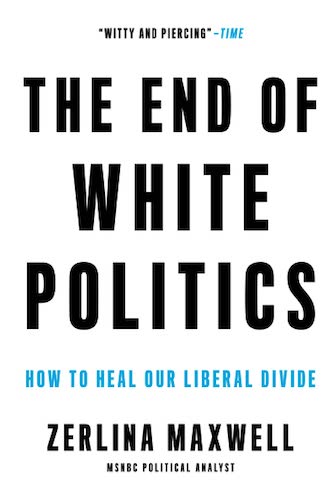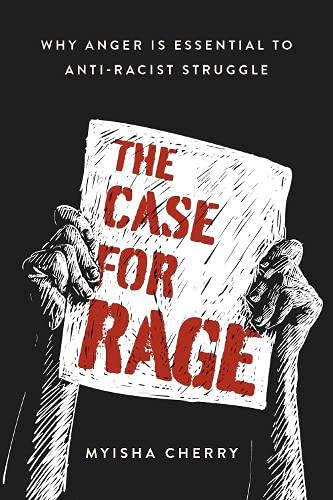
Myisha Cherry著「The Case for Rage: Why Anger Is Essential to Anti-racist Struggle」
2020年のブラック・ライブズ・マター運動の盛り上がりやそれへの反発や批判を受け、反人種差別運動における「怒り」の役割とその必要性について書かれた本。著者は黒人女性でクィアの倫理哲学者で、同じく80年代を中心に活躍した黒人レズビアン作家&詩人オードリー・ロードによる有名な演説「The Uses of Anger: Women Responding to Racism」で表現された、社会的公正の実現に繋がる「怒り」を「ローディアン」な怒りと定義し、それが過去の反人種差別や反性差別の運動で果たしてきた役割を指し示す。著者の言うところのローディアンな怒りとは、差別に対する怒りを復讐や破壊に向けるのではなくより公正な社会を作るための動機の根源となるもので、一見「怒り」の感情とは正反対とみなされる「隣人愛」を掲げたキング牧師はじめ、多くの黒人活動家たちに共有されてきた。
この本の前半ではローディアンな怒りを含む、人種問題に関係する5つの異なるタイプの怒りが定義されるけれど、ローディアンな怒りを良く見せるためか、ほかのさまざまなパターンの怒りを一方的に否定しすぎな感がある。たとえば著者が否定する怒りのパターンの1つとして「ルサンチマンの怒り」があり、その例として彼女は先住民が植民者全員に怒りを向けることを挙げたている。そのような怒りは強者に対する嫉妬であり復讐しか産まない、と著者は否定してみせる。ローディアン=「良い」怒りを社会の変革に役立つ「建設的な」怒りと定義してしまったために、そこからこぼれ落ちるルサンチマンやミサンドリーなど「非建設的な」怒りを否定することになってしまっているのだけれど、これは反差別の運動に対するよくあるバッシングをそのままなぞっているように見え、残念に思う。彼女がこのような議論をしてしまったのは、白人至上主義的な社会においてBLMやその他の反差別運動が表明する「怒り」が反対者によって不当に貶められ、かれらの主張を聞かなくてもいい口実として使われているなか、「すべての怒りが非建設的なわけではない」と言いたかったからだと思うのだけれど、「仮に非建設的であったとしても、反差別の声に耳を傾けろ」と要求することもできたはずだと思う。
本の後半では「アンガーマネージメント」として、差別に対する怒りをうまく制御して社会の変革に向けるための方法論や、アライとされる人たちが特に自分が感じている「怒り」をどう制御するかの責任を問われることなどが書かれていて、ぐっと良くなる。もし著者が白人だったらおそらくわたしはこの本を読むのを途中でやめていたと思うのだけど、最後までちゃんと読んで良かったと思えた。