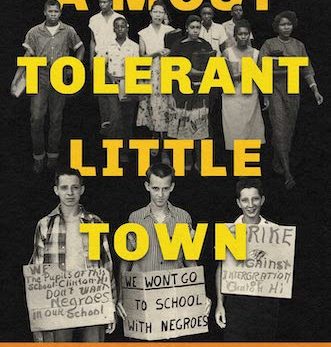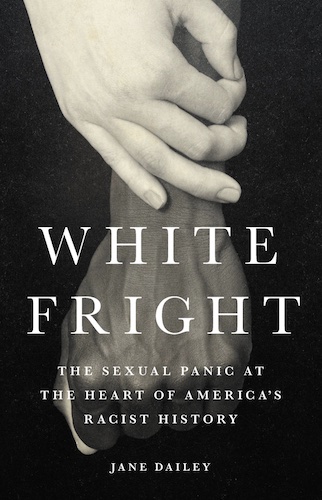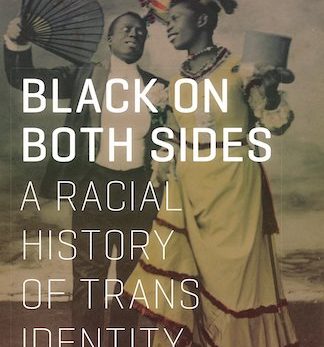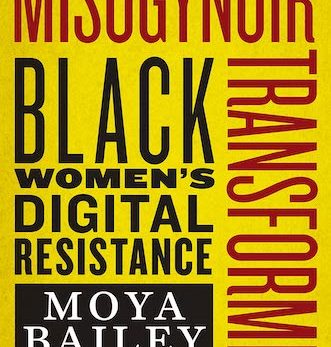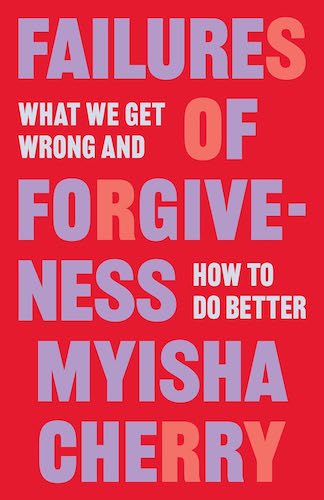
Myisha Cherry著「Failures of Forgiveness: What We Get Wrong and How to Do Better」
前著「The Case for Rage: Why Anger Is Essential to Anti-racist Struggle」では黒人レズビアンの詩人・活動家オードリー・ロードを参照しつつ反差別運動における「怒り」の必要性について論じた著者が、その鏡合わせのような関係にある「許し」の社会的・政治的な意味や効用、そしてその失敗について論じる本。
前著を読んだときにも思ったけれども、著者が哲学者として丁寧な議論を心がけているせいか、前半は「許し」とはなにか、その要件は、目的は、誰にその資格があるのか、そしてどう評価すべきか、といった論点についてこれまでの議論を押さえつつ持論を述べる内容が続くが、本当におもしろくなるのは後半に入ってから。オバマ政権時代の2015年、サウスカロライナ州チャールストンで白人至上主義者が黒人教会で起こした銃乱射事件の際、犠牲者たちの遺族の何人かが逮捕された白人至上主義者の審判に参加し、犯人に対して「あなたを許します」と次々発言したが、キリスト教的な価値観に基づいたこうした黒人たちの行為は、憎悪と人種対立を激化させることを狙って事件を起こした犯人の目論見を愛と許しで応じることで対抗した、としてメディアで広く称賛されたが、著者はその素晴らしい「許し」の裏で、ヘイトが犯人の個人的な問題であるかのように扱われ、事件の背後にある白人至上主義が放置されたことを指摘する。
この事件以外でも、白人至上主義者や警察に殺された黒人たちの遺族、とくに犠牲者の母親など黒人女性たちのもとには、事件の直後からメディアが取材に押し寄せ、「あなたは犯人を許しますか?」と質問することがよくある。アメリカの黒人コミュニティには「イエスがわたしたちの罪を赦されたのだから、わたしたちも他の人たちの罪を許さなければいけない」と考える信心深いキリスト教徒が多いので、これは「あなたは信仰は本物か、それとも偽物か」と突きつけることになる。かれらが宗教的な意味で犯人を「許す」と言えば白人社会は犯人と遺族のあいだで終わったことなのだからと社会的な人種問題と向き合う不快感(ホワイト・フラジリティ)から免除される一方、「許さない」と言えば「怒り狂った黒人」というステレオタイプを通して遺族の怒りを無視することができる。本来メディアが質問すべきなのは、「あなたはいまなにを伝えたいですか?」「わたしたちになにをして欲しいですか?」「世の中がどうなって欲しいですか?」といった質問であり、「許すか許さないか」という選択を押し付けるのは多数派社会の都合を被害者や遺族たちの尊厳に優先させることになる。
本書はほかにも、自分に対する加害行為を行った親しい男性を「許す」ような圧力を女性が受けがちなことや、アパルトヘイト政策撤廃後の南アフリカで国民和解を演出するために行われた真実和解委員会においてキリスト教的な「許し」がほかの信仰を持つ人たちに強要されたり、「許し」を拒否した被害者や遺族たちが「国民和解の意義を理解しない愚か者」的に扱われた例、職場における「許しの文化」奨励やいわゆるキャンセルカルチャー批判の問題点など、「許し」の間違った用法が加害行為によって壊された関係性を修復するのではなく加害行為の追認に繋がる問題を鋭く論じている。
…と思ったら、最後は「自分自身を許す」ことについて、また哲学的な考察に戻ってしまっていたり。良い部分はとても良いのだけれど、哲学的な考察とセルフヘルプ的な内容と人種差別や性差別についての政治的な分析が混ざってしまっていて構成的にどうなのって感じになってしまっている。きちんと読めばおもしろいのだけれど、序盤で読者が離れちゃわないか心配。