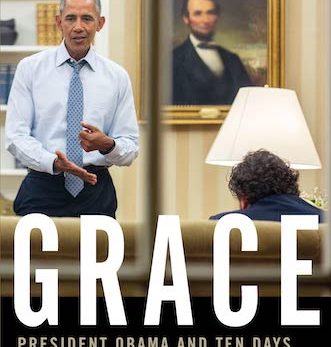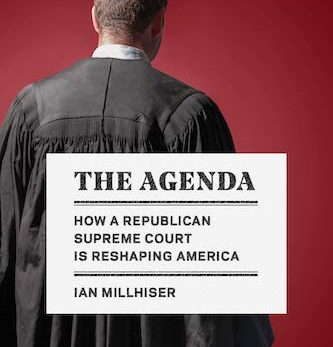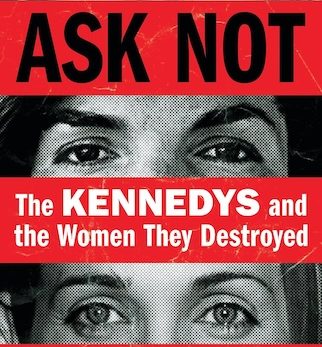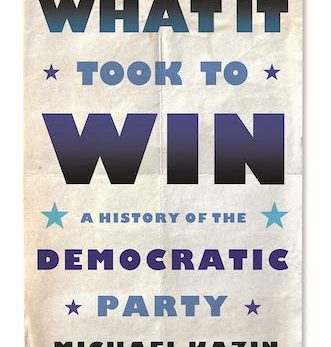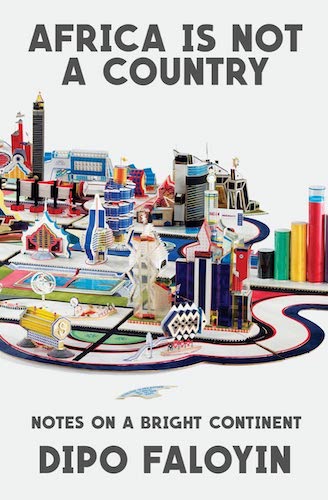
Dipo Faloyin著「Africa Is Not a Country: Notes on a Bright Continent」
ナイジェリア最大の都市ラゴスで育ったジャーナリストが欧米がアフリカに対して抱く画一的なイメージに反論する本。ハリウッド映画「インディペンデンス・デイ」の終盤近くのシーンで世界中の研究者が協力して宇宙人への対抗手段を講じているシーンではアフリカ人は一切登場せず、その後宇宙人の撃退に成功したあと世界中の人々が祝っているシーンでは上半身裸のアフリカ部族の少年たちが伝統的な踊りをしている描写が取り入れられていることに象徴されるように、欧米におけるアフリカに対するイメージはいまだに大自然・未開・貧困といったものであり、アフリカ大陸内のそれぞれの文化の違いや発展を続ける大都会、活発なアートシーンなどは滅多に注目を集めない。
本書はアフリカを見下す欧米の視線が植民地主義を正当化するためにどう生み出されたか、そして植民地主義が作り出した人工的な国境や分断支配のために生まれた統治機構がアフリカ諸国の独立後にどのような困難を巻き起こしたのか、本書でも引用されているBénédicte Savoyが「Africa’s Struggle for Its Art」で訴えているように植民地主義時代に持ち去られた美術品や歴史資料の返還がいまだに進まない理由に至るまで、欧米の植民地主義が現在も継続してアフリカの尊厳を奪い続けているか、など詳しく論じている。(Evan Lieberman著「Until We Have Won Our Liberty」で指摘されていた、南アフリカ共和国に対する高い要求と低い予想もその一種だと思う。)
欧米のポップカルチャーにおいて、アフリカは善意によるチャリティの対象としても想像される。空腹を紛らわすために大量の水を飲んでお腹を膨らませたアフリカの子どもたちの写真が本人たちの承諾なしに寄付を募る宣伝に使われ、飢饉に苦しむエチオピアの人たちのためとして多数のミュージシャンが参加したバンド・エイド(「Do They Know It’s Christmas?」)やマイケル・ジャクソンが中心となったUSA for Africa(「We Are the World」)などの試みが行われたが、それらはエチオピアで飢饉が起きた歴史的な原因から目をそらすだけでなく、特に前者についてはアフリカに対する侮蔑的な視線(アフリカには喜びはなく絶望しかない、自分たちではなくかれらがそれを経験していることを神に感謝しよう、など)や無知(アフリカには雪は降らない、雨も川もない、など)が批判された。
アフリカに対するこうした姿勢がいまも変わっていないことは、2012年に突如として流行った動画およびスローガン「KONY 2012」の騒動から見て取れる。ウガンダの反政府組織「神の抵抗軍」を率いるジョセフ・コニーの逮捕を求めるこの動画は、30分間の(YouTubeなど当時の動画サイトでは)比較的長い動画でありながら多数の有名人にシェアされた結果世界中に広まり再生回数を稼いだ。コニーは人道に対する罪や戦争犯罪で逮捕状が出ている人物であり、かれが多数の子どもを誘拐して強制的に少年兵にしたり性的人身取引をしてきたという動画の指摘を否定する人は少ないものの、動画にはウガンダの現状に対する誤った情報が多数含まれていただけでなく、当時すでにコニーはウガンダ政府軍によって駆逐されほんの200人程度の部下を引き連れて他国に隠れている状況だった。にもかかわらずこの動画を作った団体はウガンダに米軍を派遣するよう求めるロビー活動を行っており、この動画によって多額の寄付金を集めたが、その使途のほとんどはウガンダの人々に還元されることはなかった。
本書ではアフリカ主要国の歴史的な経緯や最近の情勢について詳しく紹介されており、著者の経歴とともに詳しく説明されているナイジェリアはもちろん、ルワンダやボツワナ、タンザニアなど各国の近況などについても認識を改めさせられた。また終盤では以前はアフリカ系アメリカ人のR&Bやヒップホップを真似していた西アフリカの若者たちが自分たちのアクセントやビートを使った独自のヒップホップを作っていることや、若いアフリカ人たちが安くなった機材で撮っている映画などアートの話、そしてコロナ危機を契機に各国で台頭をはじめた若い世代や女性政治家たち、さらに気候変動という共通の危機を迎えて機運が高まる汎アフリカ主義の動きなど、期待が抱ける内容。もっと知りたいと思った。