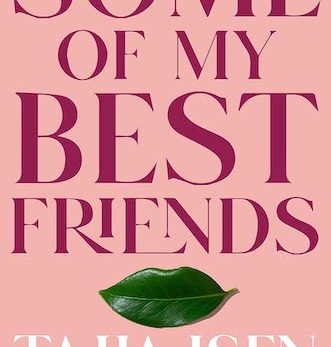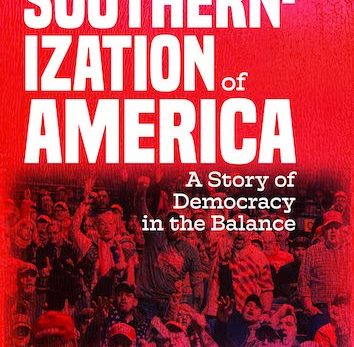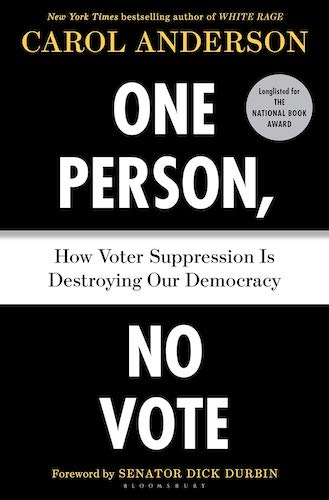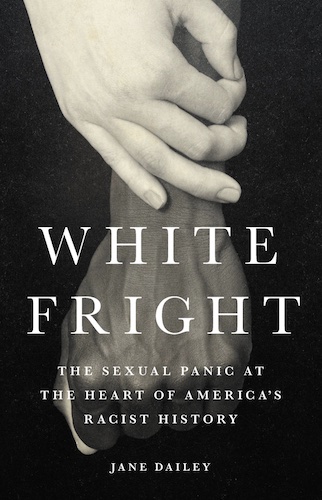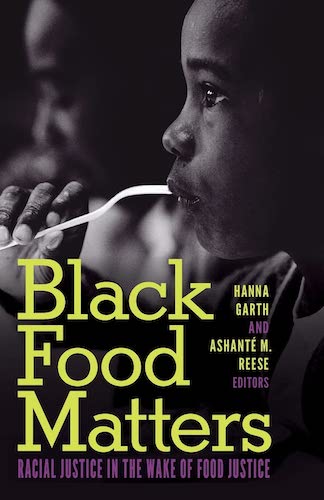
Hanna Garth & Ashante M. Reese編「Black Food Matters: Racial Justice in the Wake of Food Justice」
フード・スタディーズ(食文化研究)と人類学や地理学などの研究者たちによる、黒人の食文化についての論集。2020年出版と少し古いけれども、さまざまな側面から見過ごされてきた黒人の食をめぐる文化と歴史、その文化的剽窃や観光産業による利用、フード・ジャスティス(食の正義)を掲げる運動のさまざまなパターンとその影響など、各章それぞれとても興味深く読んだ。
わたし的にもっとも興味を持ったのは、フード・ジャスティスをめぐるいくつかの論考。米国では黒人たちが住む地域においてスーパーが出店されず、新鮮な野菜や果物が手に入らない、コンビニや小さな個人商店などで割高の缶詰や加工食品を買うか、ファストフード店でハンバーガーなどを食べるしか選択肢がなく、人々の健康が害されている、という「食の砂漠」と呼ばれる問題が論じられて久しい。また奴隷制において奴隷とされた黒人たちは白人が食べないような野菜の切れ端や固い肉の部位などを与えられ食べてきた歴史があり、ソウルフードと呼ばれる伝統的な黒人たちの食文化は体に悪い、という議論も続いている。そういうなか、政府やリベラルな白人たちは黒人たちに栄養学について啓蒙したり食文化を改善しようとするプログラムを善意で実施するも、それらは黒人たちが抱える健康格差の責任をかれらの食文化に押し付け、黒人たちが住む地域に垂れ流される汚染物質や黒人たちが経験している過酷な労働環境、貧困、警察によるものを含めた暴力、医療アクセスの欠如など、さまざまな健康被害の原因を不可視化するとともに、黒人たちが無知であると決めつけ、かれらが慣れ親しんだ伝統的な文化を破棄するよう迫る反黒人的な施策でもある。
黒人たちは食生活の重要性を理解しないわけではない。ブラック・パンサー党が「革命が実現するまでの生存」というスローガンを掲げてはじめた無償の朝食提供プログラムは、多くの黒人の子どもたちが十分な食事をしないまま学校に通っているために授業に集中できない問題を解決しようとしただけでなく、お腹が空いていては黒人たちが立ち上がり自分たちに対する暴力や抑圧に抵抗することはできない、という政治的な必要性に迫られてのことだった。FBIによる弾圧などによってブラック・パンサー党は瓦解したけれども、かれらがはじめた食の支援プログラムはロサンゼルスなどでいまも続いている。本書では言及されていないけれども、法律で定められた障害者の権利を守るための施策を政府が実施しないことに抗議して多数の障害者たちが連邦健康教育福祉省の建物に長期間立てこもった際に、兵糧攻めをしていた政府の警備員を押しのけて施設内に毎日食事を届けたのもブラック・パンサー党だった。まじカッコいい。
黒人たちはソウルフードやマカロニ&チーズ、フライドチキンなど「不健康的」とされる伝統的な食文化を守りつつ、Ruha Benjamin著「Viral Justice: How We Grow the World We Want」でも紹介されていたように新鮮な野菜や果物を手に入れられるようにコミュニティーガーデンでそれらを育てるなどの活動も行っている。しかしそういった活動においては、コミュニティの中の人たちが自分たちでなにをどこにどれだけ育てるか、どう配給するかなどを決めることが必須であり、政府や外から来たリベラル白人たちが押し付けて成功するものではない。これは「食の正義」の考えをさらに推し進めた、「食の主権」という主張に繋がる。
ほかにもさまざまなおもしろい論文が収録されていて、食文化やそれをめぐる政治の複雑さと豊かさが感じられる良い本だった。ブラック・フード・スタディーズではほかにPsyche A. Williams-Forson著「Eating While Black: Food Shaming and Race in America」も参照。